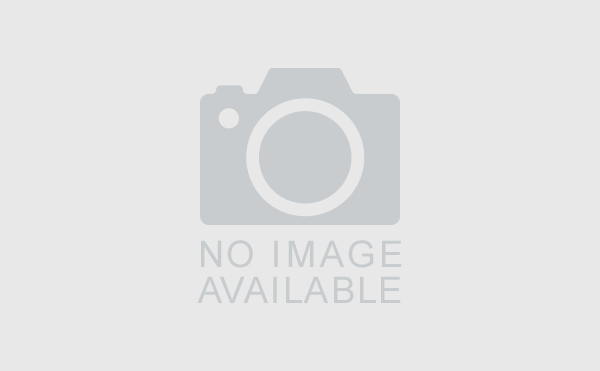トランプ関税と反グローバリズムの風潮がもたらすもの
- 相次ぐトランプ関税の波紋
日本でも大きな問題として扱われているのが、4月2日からは世界各国との相互関税の発表、また、4月3日から発動する自動車への追加関税措置の件です。相互関税については、予想以上に税率が高く衝撃的な発表でした。また、輸入される自動車に関して、25%の追加関税は日本の影響も大きいものです。トランプ大統領は、「外国の車の価格が上がれば、アメリカ産の車が売れるのでまったく気にしていない」と述べています。追加関税は日本では24%でしたが、ベトナムでは46%と高関税が発表されたときには、私自身は日本、ベトナムだけではなく世界に大変な不況がやってくると覚悟をしたくらいです。
その後、相互関税の発動は90日間延期の措置が取られました。延期を発表した理由は、米国債が売られ始めて、米国から資金が流出し始めており、放置できなくなったからだと言われています。そのことは米国債が暴落する可能性があるとみなされたことです。別の言葉にすると米国の信頼が壊れかけたことであり、一度壊れた信頼はすぐには回復ですることができないと思われます。
ところで、今までの米国を含めた世界経済の発展の動きは、グローバリズム(グローバリゼーション)の拡大の過程とみることができるでしょう。第二次大戦後世界は米国が自由主義陣営の盟主を自認して国際秩序の構築に役割を果たしてきました。1991年ソ連崩壊で唯一の超大国になりましたが、そこに俄然影響力を持ってきたのが中国の成長でした。今回のトランプ関税は中国の台頭が背景にあるとは思いますが、今回の一連の行動は、第二次大戦後の自由貿易体制の解体にとどまらず、世界秩序の解体にもつながるのではないかと思えるほどのインパクトがあります。
米国による関税引き上げはそのグローバリズムに逆行する動きです。そもそもグローバリズムという概念は、新たな世界の発見から進みましたが、それは新大陸の発見や西洋列強の植民地政策です。その後、イギリスで産業革命がおこり、蒸気船、鉄道、電信の技術が生まれたことでグローバル化は世界に波及することになりました。米国の発展もこのグローバル化による成果ともいえるでしょう。
1930年代は世界恐慌に陥り景気低迷しました。その際に当時の米国フーバー大統領がとった政策が、関税を引き上げて自国経済を立て直す政策でした。1930年に制定された「スムート・ホーリー法」ですが、米国は平均で関税率を59.1%に引き上げる政策でした。各国も報復関税を導入したことで、世界は貿易が縮小し、更に不況が進みました。その中でグループを組めるところは、自国の経済を守るためブロック経済化に進みました。組めないところは不況から抜け出し、失業者を削減するためにも軍備拡張に進みました。
グローバリズムが進行することにより恩恵を受けていた米国ですが、時間を経て今ではグローバリズムに逆行する政策を取ろうとしています。なぜ、米国が反グローバリズムの方向に舵を切ろうとしているのを考えるのが今回の論点です。グローバリズムが何をもたらし、何を壊したのかを見ていき、反グローバルの動きにも注目していきます。
2.グローバリズムが拡大した経緯
グローバリズムが広く言われるようになったのは、インターネットが普及し、情報通信が格段に進歩したことに起因していると言えるでしょう。同時に飛行機をはじめとする輸送手段が発展したことも重要で、コストをかけずに国や地域をまたぐことができるようになりました。
また、1991年にソ連が崩壊して冷戦が終結した結果、二つのグループに分かれていた国々の垣根がなくなりました。西側の資本主義陣営と東側の社会主義陣営が融合し始めることになりました。経済格差がまだ大きかった東西諸国でしたが、西側が東側の安い人件費を利用するようになりました。東西の取引も拡大したことから、世界の分業制も広がり、労働力の安い地域への工場移転が進んでいきました。
思想の面では、米国を中心に新自由主義的な経済政策も時代を動かす力になりました。日本でも金融業界の規制緩和や雇用制度の規制緩和により、社会全体で流動化が起こり、非正規雇用が増大したのもこの時期になります。このような新自由主義的な経済政策とは、政府による市場の介入や規制を最小限にして、自由競争を重んじる考え方です。経済活動や貿易の規制を排除したことで、グローバル化がますます進展しました。
そのあたりから米国で成長し始めたのが、ビックテックといわれる新興企業たちです。GAFAとかGAFAMとか言われることが多い、グーグル、アマゾン、フェイスブック(現メタ)、アップル、マイクロソフトなどの企業です。これも規制の撤廃などグローバリズムが寄与しているように思います。そしてそれらの企業は、グローバリズムの波に乗って多国籍企業に成長していきました。それらの企業は納税地も、最適な納税地を選べるようにグローバリズムの恩恵を受けました。米国が経済的に繁栄している要因はグローバリズムで成長した企業によるものと思います。
企業は利益を最大化するために、国境を越えることが経営の常識になっていきました。より安い資源を利用して、より安い労働力の確保することによって、より企業は利益を上げられるようになりました。法人税などどこの税率が低いかも同様に選択されるようになりました。特に製造業は、人件費の安い国や地域に工場を移し、生産コストの安い場所で製造するようにもなりました。それら製造業の移動に伴い、部品調達の商社、物流会社、コンサル系の会社なども海外シフトを強めていきました。それが地球の球体のなかで最適な場所で事業を進めるかが求められた考え方が、グローバリズムの進展を支えました。
3.グローバル化のメリット・デメリット
資源や資金が不足している新興国や発展途上国においては、国境を超えて働くことで母国の家族への送金も可能となり、貧困から脱することもできるでしょう。また他国の技術や文化を学ぶことで、将来的に母国への発展に寄与することができるでしょう。また、グローバル化によって最適な場所がそれぞれ分散することで、国際的な分業が進み、最適な国での効率的な生産活動ができるでしょう。
グローバル化のメリットは、まだ貧しい国の人たちにとっても希望を与えるように思います。グローバル化の意味は最適な地域を選ぶことで、貧しい国は労働力の供給先になれること、資金力のある国は海外進出することで、一国のみに依存する不安定化のリスクを避けることにもなりますし、市場の拡大を得ることもできます。世界のあちこちに技術や知識が広がり、世界全体の繁栄に寄与することになるでしょう。
しかし、グローバル化することでデメリットと考えられることも顕在化してきました。例えば米国では最適な生産地が自国以外に移ってしまいました。ラストベルト(錆びついた工業地帯)と呼ばれる五大湖周辺のミシガン州、ウィスコンシン州、ペンシルベニア州などの地域は、鉄鋼、自動車産業の中心地でしたが、海外にシェアを奪われていきました。この地域のことをラストベルト3州と呼び、大統領選挙の勝敗を分ける重要な地域といわれていました。結果は明らかにトランプ再選の原動力にもなっています。
製造業は人件費の安い地域に移動してしまいました。グローバル化は世界全体での競争によって最適な場所が決められていくのです。その結果、世界の工場であった米国ですが、アジア諸国の成長により、日本や中国に工場が移転しました。現在では、日本から東南アジアに移転しようとしています。
また、賃金が相対的に高い国には、雇用を求めて移民する労働者が増えることにもなります。現実に米国では、中南米からの移民が急増しており、将来白人がマイノリティになろうとしています。その結果、従来の労働者は給料の安い移民に雇用機会を奪われたり、給与水準が下がったりすることで中流層が減り、貧富の格差が広がる傾向が出てきます。米国では特に顕著な二極化が進んでいます。
グローバル化とはそもそも競争が激化する社会ですので、資金力のある国が市場を独占できるようになります。グローバル化の進展により、日本の産業界でも変化があります。労働集約型の産業、例えば縫製業などは賃金の安い東南アジアなどで生産するようになりました。また、自動車産業はまだ健在なものの、電気機器の製造は中国や韓国にシェアを奪われてしまっています。
4.反グローバリズムとしての保護貿易が目指す戦略
自由貿易の理念の下でグローバリズムが展開していた世界ですが、米国を筆頭に保護貿易に方向に進む国が出てきました。保護貿易とは国際競争から自国の産業を守るために関税を強化し、輸入量の規制をして外国製品の輸入を制限する政策です。このことで国内産業の発展や雇用の安定を図ろうとする政策です。
保護貿易策をとることで外国製品の流入を抑え、国内企業を価格競争から守ることができます。それにより国内産業の競争優位性が高められて、雇用も維持されることになるでしょう。国家戦略としても他国への依存度が低下することで国際変動や外部圧力に対する耐性は強化することができるでしょう。ただ、このようなことができるのは国を閉じても自力で生きていける大国以外はできないことでしょう。ただし、国内産業を守るだけでは、市場での競争力が低下し価格競争や品質競争も起こりづらくなり、長期的に見れば国際競争力を失うこともあり得る話です。
保護貿易は明確なデメリットもあります。その政策は消費者への影響や他国への影響が発生します。関税が高くなるので輸入品は価格が上昇しますから、価格に転嫁されて、消費者は高い製品やサービスを買うことになります。米国ではインフレ抑制が喫緊の課題でしたから、さらなるインフレ傾向が高まることも懸念されます。一部ささやかれているのは、不況下でのインフレと言われる「スタグフレーション」の可能性です。
対外的な問題も拡大が避けられないでしょう。関税を上げられた国にとっては、価格が高くなるので競争力が低下し、輸出の数量が落ち込むことになります。日本もそうですが、貿易で経済を維持してきた国は甚大な影響に陥ります。国際間の経済摩擦が高まり、国際的な緊張も高まることになるでしょう。相手国も報復関税をかけることで、保護貿易策を取った国の輸出産業にも影響がでることでしょう。
保護貿易政策が取れる国は、国土が広く人口も多く、産業も幅広い分野で成長している国以外は取れません。結果として保護貿易の傾向が強い国は、米国、インド、中国などに限られています。大国の論理が優先されて、世界経済は小国の淘汰に進んでいくのでしょうか?米国のとろうとしている保護貿易は、小国の未来に暗雲を漂わせているとも言えます。
5.有力国が保護貿易に進んだ時代
歴史上有力国が保護貿易に進んだ時代があります。その時期は1930年代になりますが、1929年以降の世界恐慌に見舞われた時期です。世界恐慌の中で帝国主義国は自国や自国グループだけでも経済危機を乗りきるためにとった自衛策が保護貿易でした。それぞれ市場や原料の供給先を囲い込み、それ以外を排除する経済圏の設置を進めました。
世界各国が輸出不振に陥る中で、国内資源や植民地を持った「持てる国」は、経済圏(ブロック)を作って生き残りを図りました。主要国の決済通貨を軸にしてブロック内の関税だけは軽減して、その他域外からの輸入には高関税をかけて自国内とそのグループの産業を保護するための保護貿易を実施しました。
イギリスは大英帝国から英連邦という名称に代えて、1932年から関税ブロックを作りました。一方米国は南北アメリカ大陸を中心とするドル経済圏を作りました。フランスを中心としたグループはオランダ、ベルギー、スイスとフランス植民地を加えてブロックを作りました。
その一方で「持たざる国」であったドイツ・イタリア・日本は、自給自足圏を確保するために軍事的侵攻の道を選ぶことになりました。ドイツは排外主義を掲げるナチスが政権を握ると東ヨーロッパに活路を求め侵攻しました。イタリアはバルカン半島やエチオピアへの侵攻を進めました。日本は「大東亜共栄圏」を掲げて東アジア、東南アジアに侵攻したことが米国などの連合国との軋轢を拡大しました。
その結果「持てる国」のグループと「持てない国」のグループが対立して連合国と枢軸国とに二分した第二次世界大戦に発展しました。それぞれのブロックを形成して、自国グループ以外を排除する保護貿易の結果として、そこから経済利害から外れたグループのもがきが紛争の引き金だったとも言えます。
その経済ブロックを作り戦争に至ったことを反省して、戦後の1947年「貿易と関税に関する一般協定(GATT)」が制定されて、貿易の自由化と関税の軽減に関する交渉が行われることになりました。それが約100年前の保護貿易に至り、世界戦争にまで発展してしまった歴史です。それから約1世紀後、また保護貿易という亡霊が現れました。
6.ベトナムで製造する西側諸国メーカーの存在と世界秩序
米国の保護主義の背景には、中国の台頭による覇権競争の側面があります。今回、ベトナム、カンボジアを含めた東南アジアにも高関税が課せられようとしました。これは中国近隣の国が中国からの工場移転を受け入れていると想定されているためです。カンボジアは49%、ベトナムは46%、タイ36%などとなっています。さすがに一時停止を発表しましたが、中国と米国は相互関税の引き上げの応酬です。米国には中国製品も大量に入っていますから物価上昇は必ず起こることでしょう。
確かに近年はベトナム、カンボジアは米中貿易摩擦の影響があり、中国から工場を移転させる動きが出ていました。日系企業の中国の工場縮小とベトナムへの生産移転の動きもありました。米国政府としてもその事実はわかっています。ただ、グローバル化の中で、より人件費の安い地域で製造することで、価格を抑えて競争力を上げていたメーカーもあります。それは中国からの移転とは関連がなく、人件費が安いわりに高品質であり、生産地として最適であったことも要因です。
そのような代表的な企業を紹介しましょう。韓国の電子製品メーカーのサムスンは、ベトナムでスマートフォンを製造し、米国は主要な輸出先です。米国のスポーツ用品メーカーのナイキのシューズは、主にベトナムで生産されて輸出されています。また、米国のアパレルブランドのGAPの生産地はベトナムやインドネシアの東南アジアです。アップルが販売するアイフォンのカメラ部分は、ベトナムに設立した日系工場で生産し、米国に輸出しています。私もこの会社にご挨拶訪問をしたことがありました。相互関税を引っ込めないとなると、中国とは関係がない企業も大きな痛手を受ける可能性があります。東南アジアの国は、中国、韓国、日本、台湾の影響もあり、自由貿易協定を拡大しながら最適地で生産する方向に進んでいました。それが今回のトランプ関税で壊されようとしています。ベトナム、カンボジアなど高関税が発動したら、新興国にも負の影響が出てくることでしょう。
ベトナムで長年勤務している私の感想からいうと、今回のトランプ関税の重大な欠陥があると思います。それは、各地域の賃金の格差に圧倒的に差があることです。実際米国とは5倍以上の賃金格差があるのです。ベトナムの製造業のようにトイレに行く時間も制限されても、地道に作業を続けられる人たちに米国人が勝つことは考えられません。新興国が安い製品を提供できるのは、賃金に比べての優秀な製品ができる外国での製造のほうが、圧倒的に有利なのです。まだ、貧しいから一生懸命働くのです。製造業を自国に移せばうまくいくということはあり得ません。それを給料が高い国で関税によって解決することは不可能だと思います。賃金の差があることの不理解が招いているのだと思います。米国大統領になれる人は、資産がある人しかなれません。選挙に膨大な資金がかかるためです。かつて米国が繁栄した象徴の産業である、鉄鋼や自動車産業の復活が関税で取り戻せるとは思えません。
また、中国も不動産バブルの崩壊など経済の立て直しが急務の状況です。1990年代の日本のバブル崩壊時には、中国の急速な経済成長で日本経済が支えられた時期もありました。しかし今回は、中国も以前のような余裕はありません。アジアの新興国も経済の悪化に苦しむ中で、近隣諸国とのつながりを模索していくことになるでしょう。中国はそれらの近隣諸国との関係を強化し、自由主義陣営を瓦解させるきっかけを作ることに力を注ぐことでしょう。その点では世界秩序の変更が起こるきっかけになるかもしれません。
一方でヨーロッパも経済的には調子がいいわけではありませんが、EUのグループ内で協力を模索する構図になっていくだろうと思います。ロシアの暴発を抑えるために、米国の力を期待できないとなると、EUの国同士で助け合う構図になるでしょう。
米国も「世界の警察」という高コストな地位を捨てながらも、中国の覇権は阻止する方向で世界戦略を進めているようになるように思います。考え方によっては米国が、世界の覇権国である立場から変わるきっかけになるかもしれません。
中国の習近平主席は、トランプ関税発表後の4月中旬にベトナム、マレーシア、カンボジアの東南アジア3国を歴訪しました。その中で習主席は各国と中国が「運命共同体」を構築するために努力をすることを表明しています。また、東南アジアの大国インドネシアは、BRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの頭文字をとった名称)に2025年1月に正式加盟しました。東南アジア諸国も新しい関係構築を急ぐなどそれぞれの国の判断が注目されています。
米国の一部の人たちは、かつての米国に郷愁を感じていて、アメリカを復活させることに夢を持っています。しかしながら、世界はどんどん変わっていますので、かつてのアメリカンドリームは簡単には戻ってきません。第二次大戦後、強国が一方的に小国を征服してはならないというルールが守られていました。ところがロシアのウクライナ侵攻の発生やイスラエルのガザ地区への侵攻など、最近は戦後秩序が壊れ始めているのではと感じます。「台湾有事」もあり得ない話ではなく、そのようなことが発生すれば日本も影響されますし、米国が台湾を守るということも断言できません。イスラエルのガザ侵攻でイスラム諸国の米国離れもありうる中で、今後の世界秩序がどう進むか暗雲が漂っている気配を感じています。
以上