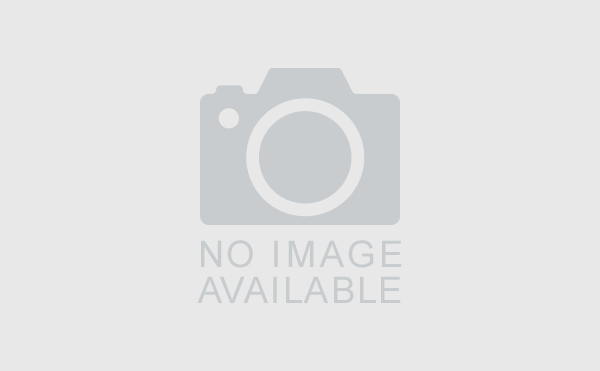時代の潮目が変わる予感のある2025年
- 「ホワイトカラー消滅」を読んで
2025年を迎えた新年にまず今年はどんな年になるだろうと考えましたが、どんな年になるだろうと思う前に、時代に合わせて自分自身は変化しないといけないことを感じます。今までと同じことだけやっていると、停滞している自分を発見することになります。その点で今年はどう変わっていこうとするかを考えないといけないと思います。
さて、時代は大きな転換点を迎えていることを感じさせた著書を最近読みました。「ホワイトカラー消滅」(NHK出版新書 富山和彦著)がそれです。少子高齢化による深刻な人手不足になる中で、それに並行してデジタル化の進展により急激な人余りも同時に進行していると言います。人手不足はローカル企業で生まれ、人余りはグローバル企業で顕著になっていると言います。
デジタル化やAIの普及に伴って、今まで企業で中心的な役割を果たしていたホワイトカラーの仕事がどんどん減ってきていると言われます。明治維新の革命的な変化によって武士階級が消滅していったように、ホワイトカラーがこれからの時代消滅に向かうことを予言しています。征韓論や西南戦争は仕事を失いかけていた武士たちの最後の抵抗の表れとも見ています。
ホワイトカラー層で生き残る可能性があるのは、経営する領域まで確保できる能力を身に着けた人くらいで、通常のルーティンワークしかできない人はAIに仕事が移っていくとしています。ただ、一部では人余りでも一部の領域は人手不足になっています。著者は少子高齢化社会の中で、人手不足に分野は増えており、ホワイトカラーがその分野に置き換わっていることで構造転換のチャンスと捉えています。
経営の能力を身に着けられなかったホワイトカラー層がどのような方向に進むかは、生産性の高いエッセンシャルワーカーになることを提唱しています。エッセンシャルワークの意味としては、現場での仕事と理解すればいいと思います。エッセンシャルワークというと肉体を使った仕事のように感じますが、医師や教師やパオロットなどもエッセンシャルワーカーとして捉えています。自身で身に着けた技術や知識を使ってその現場で能力を発揮しているからです。
エッセンシャルワーカーとの言葉が広がったのがコロナ禍の時期になります。コロナによってどんな仕事が重要で、社会を支えているのかが知られていったものと思います。ホワイトカラーの仕事は在宅勤務でも可能でしたが、現場で行う必要な業務は在宅ではできません。しかしデジタル化の進行によってコンピュータやAIに任せられるホワイトカラーの業務はどんどん増えています。その意味で、コロナ禍はホワイトカラー消滅のきっかけを与えた時期だったと言えるかもしれません。
では、そのような技術も知識も持っていないホワイトカラーが、どのような方法で技術や知識を身につければいいのでしょうか?富山氏は福沢諭吉の「学問のすすめ」に書かれているように実学から学べと言っています。仕事を進めるためには基本がしっかりしていることが大事です。これからの時代はローカル企業の人手不足にどうかかわっていけるかが重要だとしています。ホワイトカラーで身に着けた基本がしっかりあれば、なんでも自分でやらなければいけないローカル企業で能力が発揮できると言います。ローカル企業と言っても地方にある企業という意味だけではありません。都会に存在してもその地域に限定した仕事を行っている企業はローカル企業としています。
円安で外国人観光客は増えています。物流や交通などの事業も人手不足に苦しんでいますが、ホワイトカラーがそこで身に着けた実学を活かしてエッセンシャルワーカーに変化していくことがこれからの時代だとしています。ある面危機感を持ったうえで、来るべき時代に準備できた人が生産性の高いエッセンシャルワーカーになっていくことができるのでしょう。
2,日本とは異なるベトナムのZ世代
一方でベトナムの目を転じてみると、必ずしも日本と同じ方向には向かっていないことを感じます。ところで、Z世代という言葉が広く使われるようになっていますが、どんな表現なのでしょうか。主にインターネットの普及が進みだした1997年から2010年くらいに生まれた世代を指す言葉で、デジタルネイティブとの表現も使われます。ベトナムのZ世代は8割以上が就職する際には、給与と福利厚生を重視と答えています。同時に週25~35時間程度の短い労働時間やハイブリットワークと言われるオフィスワークとテレワークを組み合わせたワークスタイルを好む傾向があると記事に出ていました。
ところで先日、ベトナムでIT会社を経営している社長から聞いた話を伝えましょう。来年の給与改定に向けて入社して1年程度の社員と給与交渉を始めたようです。10%程度の昇給案を提示したところ、その程度の増額では納得できないとのことでサインを拒否したそうです。その様な社員が複数発生したと聞きました。その社長はそれ以上の増額を認めるつもりはないと言っていました。日本からのオフショア開発を受けているIT企業は多いのですが、急激な円安で利益は圧縮しています。ただ、日本で技術者採用が難しいこともあり、オフショア開発の依頼は減っていないとも言います。
では、ベトナムのZ世代はこのような過大な給与の増額を望むのでしょうか?一つはベトナム自体が経済成長中の国であることから、毎年一定の給与上昇は当たり前と考えられている社会であることです。もう一つは、Z世代はSNSの利用頻度が高く、同じ世代の人たちと密接につながっていることがあります。そんな仲間の一人が大幅に給与の伸びたことを聞くと、自分も増えることは当然だと思うようになります。SNSの情報のみに傾斜して、会社がどのような経営努力をしているかなどには関心はありません。
一方、SNSでZ世代の人がフェイスブック(Facebook)、ユーチューブ(YouTube)やチックトック(TikTok)などで成功して高額を稼いでいる人がいると知ると自分でもできるかもしれないと幻想を抱く人もたくさんいます。また、起業すれば儲かると簡単に考える人もいます。起業に関しては、日本でも同様ですがそんなに簡単なものではありません。SNSで成功者を知るとその気になる人も多いのがベトナムの特徴です。Z世代は特定の仲間からの情報やSNSへの依存から、根拠のない自信を持っている人が多い傾向があると言われています。
ベトナムでは家族のきずなが強く、最も大切なのが家族と答える人が多いのが特徴です。Z世代も例外ではなく最も大切なものとして家族と答える人が8割にも達します。Z世代の自信過剰は家庭教育の要因も指摘されています。ベトナム人の親たちは、人口の都市集中や少子化が進んでいることもあり、過保護な子育ての傾向があります。子供たちは親に怒られることも少なく、幼いころから自分を優秀だと思い込み成績や実力に幻想を抱くようになります。
また、もう一つの側面は、学校で体育(ベトナムでは副科目で重視されていない)や部活などもほとんどないため、他人との比較にさらされる機会も少ないのです。日本では必ず行われる学校での運動会もありません。この点では自分は劣っていることを知る機会もありません。勝ったり負けたりする経験も少ないことが、挫折や失敗から立ち直る精神力を築くことなく若い時期を過ごすことになります。挫折や失敗の経験が少なく、自分が思うことは何でも通じると思いすぎてしまうのです。日本のZ世代の自信のなさに比べると、ベトナムのZ世代の自信があることはいいところでもありますが、自信過剰だけではバランスの良い人間にはならないように思います。
3,103万円の壁は高度成長期の遺物?
昨年緒衆議院選挙で躍進した国民民主党が選挙戦で主張し、国民にも一定の支持が集まったと思われるのが、「103万円の壁」問題でしょう。103万円が基準になるのは、基礎控除が48万円で給与所得控除が55万円となり、合計して103万円までが所得税を免除される仕組みです。主婦がパートなどをした場合に103万円の収入を超えると所得税が発生します。それにより手取りが減るので、103万円を超えないように調整せざるを得なくなる問題を指しています。物価も上昇に最低賃金も上昇するようになり、103万円の壁が時代に合わなくなっている面は確かにあるでしょう。103万円の壁以外にも、社会保険の加入義務が生じる106万円の壁、扶養から外れる130万円の壁など、あらゆるところに壁はあります。
なぜ、このような壁が作られるようになったかは、社会の仕組みと密接な関係があります。日本では高度成長期と言われた時代がありました。1955年から1973年くらいを指すと思いますが、現在とは違う日本の空気がありました。国民総生産を10年以内に2倍にする目標が、1960年末に閣議決定された所得倍増計画でした。実質経済成長率が毎年10%前後にもなる今では考えられない時期でした。このような高度成長を進めるために役に立った仕組みがありました。日本の企業は終身雇用や年功序列などの仕組みを使い、従業員の企業へのロイヤルティーを高めて、企業戦士ともいえる人間形成を進めていきました。その当時は転職する人もそれほど多くはありませんでした。長く働いたほうが給料は多くなるからです。
そのうえで工業化が進んだ都市部で働くようになった核家族には、標準的な生活が求められました。標準的な団地に住んで、標準的な家庭を持ち、標準的な生活をするようになっていきました。正社員のサラリーマンの夫と専業主婦の妻と平均2人の子供を持つ家庭が維持されてきました。大量生産、大量消費を求められる工業化の社会においては、標準的であることが重要だったのです。その当時の仕組みは、標準的な家庭を維持できるために作られた合理的なモデルだったのでしょう?核家族化が進んだ過程では妻は専業主婦であることが求められました。その仕組みを維持させるためにできてきたのが、103万円の壁などの税制度や社会保険の仕組みです。そこで国民の9割程度が中流意識を持つに至ったのが、高度成長期と言えるでしょう。
ただ、その仕組みが大量生産型の工場が海外に移転するようになり、IT革命が進行するようになると企業は人件費を削減するために非正規雇用が増えるなど、社会保険料を減らすような雇用形態が増えてきました。大量生産型のシステムに時代が合わなくなり始めたのです。
時代は円安になり、外国人労働者も確保が難しい時代になりました。少子高齢化の進行で労働人口が減る中で、従来の大量生産型の制度は変えなければならない時期に差し掛かっているように思います。今後の日本社会では、女性の活用、高齢者の活用なども含めて、社会保険にはすべての国民が入れるような仕組みも含めて制度変更が必要な段階になっていると思います。今回表面化した「103万円の壁」に関しては、小手先の改革ではなく、新しい時代に合わせた日本の労働力確保のための抜本的な制度改革が必要になっていることを感じています。
4,逆風が吹き荒れそうな2025年の世界経済
時代の潮目が変わり始めていることを感じます。「ホワイトカラー消滅」、ベトナムのZ世代、103万円の壁などを題材にみてきましたが、社会システムが変わろうとしていることは事実でしょう。それと合わせて地政学的な変化が進んでいます。米国の強さはまだ変わらないとは思いますが、時代は欧米からアジアに変わろうとしていることも重要な変化です。世界のGDP(国民総生産)の順位を見ると1位が米国、2位が中国、3位がドイツ、4位が日本、5位がインドになります。5位までに3つがアジアになっています。日本がドイツに抜かれたのは最近ですが、長期に続く円安の影響が大きいと思います。インドの成長速度は速く、人口も巨大なことから日本がインドに抜かれるのは確実な状況です。中国とインドに挟まれたアセアンも重要な役割を持つようになりました。
時代の変わり目を感じる年として2025年は微妙なリスクを感じる年になりそうです。そこで最終章として今年の展望を見ていきましょう。キーワードはトランプ米国大統領の登場と長引く不動産不況に苦しむ中国の存在でしょう。トランプ政権でいえば米国第一主義を発信するトランプ大統領の産自国産業保護政策です。自国の産業を守るために輸入品には高い関税をかける政策です。中国への追加関税や米国に隣接するカナダ、メキシコへの追加関税を課すことも表明しています。このことは北米3か国で連携してきたサプライチェーンを壊すことにもなります。
次に中国の問題です。不況に苦しむ中国は、習近平政権の3期目の今、厳しい経済問題を抱えています。不動産不況に加えて、若年層の失業問題も深刻です。中国国内で起こる殺傷事件も社会が病んでいることを感じさせます。そこにトランプ政権の中国への追加関税が加わることで、さらに中国は追い込まれることになります。結果として中国は成長著しいアジアやアフリカに向かうことになるでしょう。
米国も中国も自国第一主義に傾斜する中で、保護貿易に向った年代を見ていきましょう。1930年代には世界が保護貿易の方向に進みました。きっかけは米国で起こった大恐慌です。大恐慌の発生は米国の経済繁栄の中で、矛盾が拡大しつつあったことが底流にありました。労働者の賃金の抑制や、農業不況などもある中で、株式市場だけは伸びていました。誰もが株をやらないと損だと思い始めていました。
ところが第一次世界大戦の戦場であったヨーロッパの復興とともに、米国の工業製品は在庫を抱えるようになっていきました。多くの人が株を買うようになっていましたが、それが一気に暴落したのが大恐慌です。「ブラックサーズデー」と言われるニューヨークのウォール街で起こった1929年10月24日の株式市場の大暴落です。そこから世界恐慌と言われる大不況が世界を覆いました。
その解決策として登場したのが保護貿易です。米国は農業不況を救済するために1930年に「スムート・ホーリー法」を成立させ、2万以上の品目について輸入関税を引き上げました。ただ、このような関税の引き上げは、世界各国が対抗手段に出ることで、世界中で保護貿易が進み一気に世界経済を萎縮させることになりました。その世界経済が萎縮する中で自国グループだけで利益を守ろうとしたのが、保護貿易の一種であるブロック経済です。多くの植民地を持っていたイギリスとフランスは、その植民地支配をしていた地域とだけ取引をするブロック経済圏を築きました。アメリカは北米や南米の一部とのブロックを形成しました。植民地が少なかったドイツ、イタリア、日本は、貿易戦争に不利な立場にあり、領土拡張競争に発展して、第二次世界大戦の素地を作ることになりました。
歴史の教訓から考えると、日本の立ち位置が重要になってきます。孤立する方向ではなく、協調する方向で仲間を作ることが重要と思います。近年ではTPP(環太平洋パートナーシップ協定)をはじめRCEP(地域的な包括的経済連携協定)など自由貿易協定を推進してきた日本ですが、信頼できる相手を見つけて連携することは重要になるものと思います。幸いにして現在アジアが経済成長のエンジンになっています。アジアの諸国との良好な関係が維持できれば、アジアのサプライチェーンが形成されて、日本の重要な生産拠点になっていくものと思えます。円安が国力の低下をもたらしている面は確かにありますが、円安だからこそ製造業に国内回帰のチャンスがあり、日本を中心としたサプライチェーンの形成に重要な役割があるものと思います。
以上