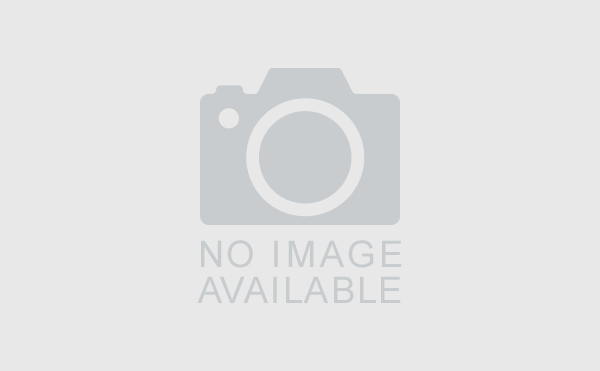世界インフレから貨幣制度・経済思想を辿る
1, 世界同時インフレの理由
現在世界は世界インフレともいえる状況になっています。半世紀ほど前の1973年に世界的にインフレになった時期がありました。それは第4次中東戦争が引き金になりました。イスラエルとアラブ諸国との戦争ですが、西側諸国が支援したのがイスラエルでした。それに反発するアラブ諸国が石油を政治上の武器として活用し、原油生産量の削減と西側への禁輸措置をとったことで、エネルギー価格が急騰したのがきっかけでした。
日本ではエネルギー価格が急騰した結果、製造のために石油の利用が多いトイレットペーパーの生産に影響が出たことから、各店舗からトイレットペーパーがなくなる事態にもなりました。1973年から数年続いたインフレは景気停滞下のインフレと言われ、景気停滞のスタグネーションと物価上昇のインフレーションを掛け合わせた造語で「スタグフレーション」と言われました。現在はその時以来の世界同時インフレが起きていますが何が影響しているのでしょうか。
この間の世界インフレは新型コロナウィルスの影響による需要と供給のバランスが乱れたことが要因と言われています。バランスの乱れとは、パンデミックの終焉から経済が再開しましたが、その間に抑制されていたモノへの需要が急速に高まりました。一方で物流の停滞や人手不足により供給が追い付かないことも、モノ不足を引き起こしている背景です。
さらに重要な要素があります。各国が金融緩和政策を行い、世の中に出回るお金の量が増加したことも要因です。これがインフレ圧力になっています。インフレ抑制のために利上げを行っている国もありますが、日本ではそれができていませんので、インフレが加速しています。長年の金融緩和政策により金利を上げられない事情もあり、円安に進んだことが食料品やエネルギーを輸入に頼る日本は、急激な物価高に見舞われているのです。
加えてロシアのウクライナ侵攻によるエネルギーや穀物価格が急騰したこともインフレを加速した要因になりました。ロシアのエネルギーの輸入規制、穀倉地帯であるウクライナの生産量の縮小による供給の減少がインフレをもたらしています。同時に地球規模の気候変動により不作も起こっており、供給が需要に追い付かないことも要因です。紛争も世界に拡大しており、中東紛争なども一部の原材料の高騰の要因になっています。
2,ケインズ主義にからマネタリズムへの変化
それぞれの時代の経済状況の中で経済政策が大幅に変わった時期があります。この100年に歴史の中で政治経済政策に大きな影響を与えた経済思想を紹介しましょう。
財政出動による景気回復を図る考え方は、ケインズ主義と呼ばれるものです。ジョン・メイナード・ケインズが提唱した考え方です。この考え方は大恐慌に陥っていた米国で積極的に活用されました。フランクリン・ルーズベルト大統領によるニューディール政策の経済理論の支柱になりました。不況下に財政出動をして公共事業を起こすことで、失業者の減少、生産の拡大、消費の拡大をもたらすきっかけになるというものです。1933年に始まったテネシー川流域開発公社の巨大ダム建設などが有名な公共事業で米国経済が徐々に復活しました。
ところが新しい経済の矛盾が発生したのが、第一章で取り上げた1973年からの第一次オイルショックの時期です。景気停滞と物価上昇が同時に起こる事態にそれまでの経済思想が機能しなくなっていました。それまでは、不況時には財政出動をして需要を刺激することで、雇用や消費が拡大して景気回復することができるというものでした。景気が上昇した時期では、財政出動を抑制して景気を調整するというものでした。ところがその時期は、財政出動を抑制するとさらに景気が低迷し、財政出動をするとインフレがさらに加速する事態になりました。この時期の問題は、コストの上昇に伴う供給側にありました。需要を刺激しても景気回復にはつながらず、ケインズ主義の限界と言われました。
ケインズ主義に代わって台頭してきた経済思想がマネタリズムと言われる考え方です。その考え方は貨幣供給量(マネーサプライ)が経済に大きな影響を与えるという経済理論です。政府が介入するのではなく、自由に経済活動する機会を与える仕組みが、経済を復活させると考えられました。金本位制も崩壊していたこともこの理論が力を持つ要因になりました。貨幣の供給量は国や中央銀行によって自由に調整できます。貨幣を市場に追加して供給することでインフレ傾向にはなりますが、供給側が潤沢な資金を活用しやすくなります。政府が介入しなくても民間が貨幣を自由に使うようになります。中央銀行が貨幣供給量を適切にコントロールすることが、物価の安定と持続的な経済成長には重要だとの主張であり、有力な提唱者はミルトン・フリードマンでした。
その経済思想に連携して出てきたのが、「新自由主義」の考え方でした。古典派経済学のアダム・スミスの「自由放任」を徹底する考え方です。そのため新自由主義とも呼ばれました。市場原理に基づく自由な競争によって、経済の効率化や発展を目指す考え方です。政府は小さな政府であるべきで、民営化や規制緩和を推進することを目的とされました。経済変動の対応は大きな政府による財政出動ではなく、民間の自由な経済活動を阻害しないことが重要とされました。自由な競争の環境を作ること、その中で成功も失敗も自己責任であることが前提になりました。この時代は自己責任を強調する考え方になり、社会保障の低下や貧富の格差拡大が進んだとも言われています。
新自由主義に基づいた主な政策は次のようなものでした。日本では国営企業、国鉄、電電公社、郵便局の民営化、派遣労働の解禁や非正規雇用の拡大、金融制度改革として「金融ビックバン」と言われる金融制度改革で銀行などの統廃合が進みました。新自由主義的な政策で有名なのは、米国のレーガン大統領や英国のサッチャー首相が行った政策、日本では小泉首相の郵政改革などが有名です。
3,現代貨幣理論(MMT)と現在の経済政策
金本位制が崩壊して貨幣供給量で経済活動を調整する考え方から、財政出動を加えて経済運営する考え方が出てきました。財政出動は政権が国民からの支持を受けやすい政策でもあり、SNSの普及で政治家が大衆を意識する傾向が拡大しました。SNSを上手に使って大衆の支持される候補者が有利になりました。
金融緩和と財政出動を同時に実行する経済理論が、現代通貨理論(Modern Monetary Theory、以後MMTと言う)という一風変わった考え方です。ケインズ主義の側面と新自由主義の側面を組み合わせたように見えるのですが、特徴的なのが財政の健全化の主張と対極の立場になります。
独自通貨を持つ国は自国通貨建ての国債を発行する限り、財政赤字が膨らんでもデフォルトは起きないと考える理論です。そのためお金は必要に応じて自由に発行すべきと考えます。お金はゼロから作られるが、中央銀行から発行した際に信用創造(価値があると信用させること)によって、利用価値を与えられるとの考え方になります。金本位制や中世の貨幣理論は財源の裏付けが必要でした。中世ではお金を返せなくなると徳政令を出して借金を踏み倒すこともありました。しかし、銀行制度ができて以降の「お金」は、信用創造の賜物であり、無から信用という価値が作られると考えるのがMMTです。プライマリーバランスという言葉がありますが、国の歳入のうちで、国債ではなく、税によるものがどの程度あるかを示す指標です。財政の健全性を表す考え方です。その考えに立たないのがMMTです。
財源としての税金があるので国はお金を使えるのではなく、信用創造した貨幣の発行が先で、税の徴収は後という考え方です。使うのが先(Spending Fiest)であり、回収するのは後(TaxはSecond)と考えることで財源という考え方を否定します。
金融機関が信用創造した貨幣を使い経済を動かし、インフレを調整するために税金を徴収するのだと考えます。税として徴収したお金の価値を消すことで、インフレを抑制するのが税金の役割と考えます。確かにお金を刷りまくって信用創造したとしても、実態として価値がないと判断されれば、価値は大きく棄損します。そのために税で回収したお金を消すことが必要なのです。それをしなければ、とてつもないインフレになってしまうでしょう。
MMT考えでは税の役割としては以下の考え方を取ります。
・景気の調整
・所得の再分配
・罰金的役割(たばこ税や環境税など害があるものに課税して利用を減らす目的)
・国民が自国通貨(円)を使うことを促す役割(税は円でしか払えない)
税として徴収してお金を消すことで、自国通貨を吸い上げて、過剰なインフレを防ぐことができるとしています。インフレにならない限り、財政支出を増やし、公共サービスを拡充することができるというのがMMTの考え方です。
この考え方とは若干異なりますが、リフレ(リフレーション)という考え方があります。その考え方は財政出動には懐疑的ですが、金融政策によってデフレ経済から脱却しようという考え方です。その考え方を推進しようとする人たちをリフレ派と呼びます。その金融政策とは日銀の国債の大量買入れや低金利政策によって物価の安定的な上昇を図ろうというものです。この考え方を利用した政策の典型がアベノミクスです。
第二次安倍政権になって日銀の委員にはリフレ派が登用されました。その考えは金融の量的緩和措置を利用して、ある程度のインフレ経済を実現しようというものでした。なぜデフレ経済がいけないかというと、デフレ下ではお金を使わない方が有利であり、経済が縮小してしまうからです。ただ庶民の生活には物価が低下するデフレの方がしやすかったかもしれません。ただ、それが長く続くと給与も全く伸びなくなります。世界がインフレに進む中で日本だけがデフレに陥り、その間に個人の所得もGDP(国民総生産)も国際比率がどんどん低下していきました。
現在のようにインフレが進行したときに、さらなる信用創造でお金を作り続けるとするとインフレが進み、調整できない状態になることも危惧されます。信用創造はある程度調整する機能を持たないと、コントロールできない状態になってしまいます。現在の円安は、金融緩和(信用創造)を長期間やりすぎた要因があるのではないかとも思います。独自通貨を持つ国は自国通貨建ての国債を発行する限りデフォルトは起こらないと考えられています。しかし、相対的に円の価値が低く見られて、外貨投資などにも進みさらに円安は進行しています。
4,異次元の金融緩和とは何だったのか?
世界経済の話を進めてきましたが、最近の日本経済の話を進めましょう。安倍晋三首相と黒田東彦日銀総裁を中心に行われた政策についてです。「異次元の金融緩和」と言われる政策です。金融政策でインフレ誘導したのですが、なかなか2%のインフレの実現はできませんでした。
金融緩和のみでは足りず、アベノミクスの三本の矢という考え方で経済政策を進めました。「大胆な金融緩和、機動的な財政出動、民間投資を促進する成長戦略」がその政策です。金融緩和と財政出動というMMTの考え方にも近くなりました。この時期に起こった東日本大震災やコロナ禍は、財政出動と金融緩和の融合したMMTという考え方に近い政策運用が必要になったことも影響しているように思います。
日銀は市場の供給するお金の量を増やすために、金融機関の持っている国債を大幅に買い入れ、日本銀行券(貨幣)を市中に供給しました。買入れる国債も長期保有し、上場投資信託(ETL)などのリスク資産も保有して、量的・質的な金融緩和を行いました。しかしながら東日本大震災に見舞われたこと、またデフレマインドから市中に大量のお金が出回っても、一般庶民は消費を拡大しようとは思わなかったこと、そのような社会の空気がデマンドプル(需要拡大)によるインフレに向かうことを阻害しました。消費が拡大して物価が上昇することもありませんでした。そのため金融緩和策は長期間継続されることになりました。
日銀はさらに追加的な金融緩和に踏み込みました。2016年からマイナス金利という概念も持ち込みました。マイナス金利とは、各金融機関が日銀から発行された貨幣を当面使う用途がないので、日銀の当座預金に預ける時の金利をマイナスにするという考え方です。金融機関に渡した貨幣を日銀に預けると金利負担が発生します。そこで預けるのではなく、市中に融資するように仕向ける方策です。
この政策によって長く続いていた株安からは脱することができましたし、円安傾向が出てくることで輸出企業の業績は改善したものと思います。それは政策によるメリットということが言えるでしょう。ところが金融緩和してもデフレ脱却が難しい中で、新型コロナ禍が発生しました。政府は財政出動をせざるを得なくなりました。ヘリコプターマネーという言葉がありますが、バラマキ政策を取らざるを得なかったのです。
この間に世界が同時インフレに進む中で、金融緩和の影響が円安を招くことになり、世界インフレと円安の影響が絡み合い、日本のインフレ傾向は止まらなくなりました。これが大規模な金融緩和のデメリットと言えるでしょう。さらに今後も円安からの脱却は難しいのではと思われます。これは、国際情勢の変化の中で、防衛費の増強の考え方に傾斜していく可能性があるからです。高市首相のトランプ大統領との約束にもある防衛費の増強や米国への投資拡大などなどの財源を確保しなければいけないのですが、MMTの考えに近づいていくことが考えられます。
プライマリーバランスを重視する経済健全性を図ることより、金融緩和と積極財政の同時進行が必要になる戦時経済のような経済構造になる可能性があります。日銀の国債による金融緩和策の継続と積極財政によって、どんな経済状況を生み出すかの注意は必要です。
5,環境変化が貨幣思想を変える
第一次・第二次世界大戦下、各国は多額の軍事費が必要になり戦時国債を発行し、金の保有量を超えて通貨を発行する必要に迫られました。戦後世界経済の安定が壊れそうになる中で、国際経済の安定化を図る必要がありました。ブレトン・ウッズ体制(金・ドル本位制)によって、基軸通貨になった米ドルが金との交換を保障することになりました。
ところが米国が介入したベトナム戦争の長期化などによる財政悪化で、アメリカ国外へ金が大量に流出する事態になりました。その当時の米国ニクソン大統領が、金・ドルの交換停止を宣言した「ニクソンショック」と言われる事態の発生です。この決定でブレトン・ウッズ体制は崩壊し、金の裏付けのない貨幣制度である変動相場制に移行しました。各国の通貨の価値を管理する管理通貨制度に移行したのです。1ドル=360円(スミソニアンレートとして308円の時期もありました)と固定されていたドル円相場が、1973年から通貨の評価で変動するようになりました。
このことがマネタリズムや新自由主義を誕生させる契機になりました。そこから50年後、新自由主義的な小さな政府による自由競争を推進していた社会から、国の財政出動を進めようという大きな政府につながる考え方が登場してきました。その背景には、自由競争で所得格差が一層拡大したこと、経済成長が鈍化したことに影響を受けています。また、人々インターネットやSNSにのめり込むことで、政治家の選び方も変わってきました。自分たちにプラスの考え方を明確にしてくれる人を支持するようになり、減税や財政出動に期待するようになりました。
近年の米国の政治情勢の変化が、時代が変わり始めていることを感じさせます。一方に行き過ぎるともう一方に流れが変わり始めているのを感じます。日本でも最近は「給付付き税額控除」という考え方が出ています。減税するが減税効果の少ない低所得者層には一定の現金を給付する考え方です。高市首相も検討したいと述べている政策です。
お金の仕組みや経済の仕組み自体は、人間が作り出した虚構ともいえるものです。考え方の変化で変えることができます。貨幣経済は当初は金本位制という考え方が基本でした。発行できる通貨量は金の保有量に制限されるという考え方です。しかし、グローバル経済が拡大する中で、それに対応ができず崩壊しました。主な理由は金の保有量を超える通貨を発行できないために、景気が悪化しても金融緩和などの対策を打つことができませんでした。また、経済発展して取引量が増えても金の供給量が追いつかず、通貨が不足し経済成長が停滞することになるからです。
貨幣によって人々の行動を調整するなど、意識を変えることで実行されるのが経済政策と言えるでしょう。財政規律さえ考慮に入れないMMT理論が登場する中では、お金の量だけに左右されない生き方も必要ではと思います。経済政策や理念は時代とともに変わっていきました。自由競争による経済成長を重視する考え方の時代、財政出動によって社会保障を充実させることが支持された時代もありました。
お金とは人間が作り出した虚構です。人間にとってお金は重要ですが、お金さえあれば幸せということではありません。どのように社会とかかわれるのか、自分のやるべき課題があるのかを明確にできた人が、幸せをつかむことができるでしょう。人生は限りがありますから、お金に支配される生き方を選ぶ必要はないと思います。経済の変化を眺めてみると、お金に汲々としても翻弄されるだけです。最低限生きるのに必要なお金を手にして、生きる意味を探す努力が大切かもしれません。
以上