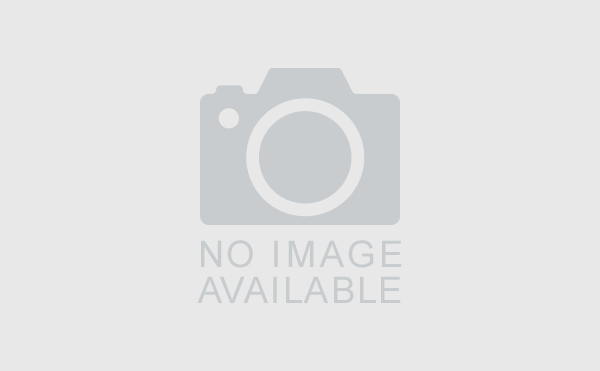国家の衰退と繁栄を分ける政治経済体制
- トランプ再選の米国と中国、ロシアの違い
トランプ氏が米国大統領に再選され1月より就任しています。矢継ぎ早に輸入関税の引き上げを発表したり、グリーンランドやガザの米国所有を主張したり、やりたい放題の発言が目立っています。トランプ氏の言動に今後の世界がかき乱されないか心配する向きも多いと思います。時代の転換点になる可能性はあるかもしれませんが、米国がとんでもない過激な国になることには心配無用でしょう。それはトランプ大統領の任期が4年のみと決まっているからです。この4年間でトランプ氏は自身のやりたいことをするでしょうが、それができるのも4年のみです。
一方でロシアは2000年にプーチン氏が大統領に就任し、2008年から2012年の期間だけ配下のメドベージェフ氏が大統領になり、その4年間は首相になっていましたが、2012年に大統領に復帰してからは継続しています。大統領選挙の縛りはあるものの、憲法改正によって最長2036年まで継続することが可能になりました。
一方中国でも習近平国家主席が2013年に就任以降、通常は2期(1期5年)までの任期を改正して任期制限を撤廃しています。そのため2023年から異例の3期目に入っています。3期目の任期は2027年で終了しますが、2024年7月の中国共産党の重要会議「三中全会」で「建国80年となる2029年までに改革の任務を完成させる」という新たな目標が示されたことから、2027年以降もトップの座に留まるのではとの見方も出ています。
北朝鮮は社会主義国ですので一党独裁の政治体制が特徴です。その一党とは朝鮮労働党であり、通常は朝鮮労働党が国家を指導するのが典型的な社会主義国のスタイルです。しかし、北朝鮮の特徴はほかの社会主義国とは異なります。トップの1名のみに権力が集中しており、党の最高指導者として絶対的な権限を持っています。それは同じ社会主義国ではありますが、ベトナムとは全く違います。更に権力が世襲される仕組みは北朝鮮だけです。金王朝ともいえる世襲制で、金日成、金正日、金正恩と続いており、1948年金日成が政権について以来、独裁体制を築いています。
そのこともあり、ロシア、中国、北朝鮮は、権力の固定化が進み強権的な支配体制が続いていると言えるでしょう。一方の米国トランプ大統領側も政権中枢の人事はトランプ氏の意向に沿い、国家に忠誠心を持つよりもトランプ氏に忠誠心を持つことを求められているように見えます。政府効率化省を率いるイーロン・マスク氏は、前回の大統領選で多額の献金を行ったことで知られています。このこともロシア政治に大きな影響を与えているオルガルヒ(ロシア新興財閥)にも似ているともいえます。
米国トランプ大統領もかなり強権的な手法をとる政治家と思います。しかしながらロシア、中国、北朝鮮との決定的な違いは、米国の大統領の任期は最長で二期8年までと定められていることです。トランプ氏は連続二期ではない珍しいパターンですが、残りは4年間で長期間に渡り権力が固定化することはありません。その点で米国とロシア、中国、北朝鮮とは決定的に違っていると言えるでしょう。
2,2024年ノーベル経済学賞受賞者
さて、ここでは冒頭の論点から、日本で購入して移動のたびに読んでいた本について触れようと思います。この本から現代政治と経済制度に関して幅広い示唆を受けることができました。日本に帰国した1月23日から2月5日の間読んでいて読破できた本です。それは「国家はなぜ衰退するのか 権力・繁栄・貧困の起源」(ダロン・アセモグル、ジェイムズ・A・ロビンソン共著 ハヤカワ・ノンフィクション文庫)です。2024年ノーベル経済学賞受賞の2名が書き下ろした国家の繫栄と衰退の原因を分析した内容です。2016年5月に日本語版の文庫本の初版が出版されました。
世界には繫栄する国と貧困から脱出できない国が存在するのは、どのような理由があるかが論考されています。この本を手にしてから、文庫上・下版で合計800ページ近くあるものですが、飽きることなく読むことができました。興味深い内容だったので紹介をしようと思いますが、まずは2024年ノーベル経済学賞を受賞していますので著者の紹介から始めます。
著者の紹介ですが、ダロン・アセモグル氏はトルコ出身の経済学者で、専門は政治経済学、経済発展論、経済理論などです。現在はマサチューセッツ工科大学の教授です。「技術革新と不平等の1000年史」(サイモン・ジョンソンとの共著)などの著作もあります。
ジェイムズ・A・ロビンソン氏は、イギリス出身で政治経済学、比較政治学などの専門でボツワナ、モーリシャス、シエラレオネなどの国の体制研究を行っています。現在はシカゴ大学の教授です。
「国家はなぜ衰退するのか 権力・繁栄・貧困の起源」の著者ではありませんが、「技術革新と不平等の1000年史」(ダロン・アセモグルとサイモン・ジョンソンとの共著)のもう一方の著者サイモン・ジョンソン氏もマサチューセッツ工科大学の教授で、この人と合わせて3名が2024年のノーベル経済学賞を受賞しました。
2024年ノーベル経済学賞ダロン・アセモグル氏、サイモン・ジョンソン氏、ジェイムズ・A・ロビンソン氏の著書はよくある経済学者の著書のような難解さはなく、歴史書のような読みやすさがありました。「技術革新と不平等の1000年史」(サイモン・ジョンソンとの共著 早川書房)は、「週刊 東洋経済」の今年の新年号で、2024年の経済書・経営書の第一位に選ばれていました。
ノーベル経済学賞の受賞者を決定したスウェーデン王立科学アカデミーは、3人の選考理由について、「受賞者たちは植民地化の際に導入された社会制度が、各国の繁栄の違いを説明する一つの要因であることを示ししました。国の間の大きな所得格差を縮小することは、現代における最大の課題の一つです。受賞者はこの目標を達成するため社会制度が重要であることを実証しました」と評価しました。
研究では、アメリカとメキシコの国境沿いにある2つの町を例に、なぜ気候が同じで人口規模も似ているのに、アメリカ側の町は豊かで、メキシコ側の町は貧しいのかという疑問に両国の社会制度の違いがあるとの答えを導き出しています。そのうえで、王立科学アカデミーは「受賞者たちの研究は、経済学と政治学の両分野で継続して行われている研究に決定的な影響を与えた」として、民主主義と包括的な制度が経済発展を促進する上で、重要な役割を果たしているとも指摘しています。
3,「国家はなぜ衰退するのか」が伝えようとしたこと
繁栄する国がある反面、貧困が継続する国があります。その要因として地理的な要因、文化的要因、無知による要因を上げる説がありますが、どれも当てはまらないと退けています。王立科学アカデミーで評価されたように、例えば米国南部とメキシコ北部の隣接した地域で、繁栄と貧困の境界ができていることは何を意味するかとして論考が続きます。
例えば中南米では先住民が築いたインカ帝国などの国があり一定の繁栄をしていました。しかしながらスペインが植民地にしてからは、先住民は収奪される側になりました。支配者が代わっても、その権力は住民たちを収奪する方向から変わりません。たとえ植民地支配から独立を果たしたとしても、権力者が住民を収奪する立場は変わりませんでした。貧しい国は一向に貧しさから抜け出せないのは、そのような収奪の体制が影響しているとします。
一方で発展する国の特徴は、収奪的な政治制度ではなく、包括的な政治・経済制度が築かれているからとしています。包括的な政治経済制度とは、そこに住んでいる人々にチャンスが与えられて、創造的破壊が起こるごとにイノベーションが起こり、多元的な発展に向かうことができる体制としています。特に発展の方向性を得た国として米国、イギリス、フランス、日本などの例が述べられていますが、それぞれの国の体制の革命的な変化が創造的破壊を誘引して、イノベーションに結びついていったと考えます。
変化をもたらす要因は、歴史的な大変化を伴う出来事があげられます。今までの体制が維持できなくなる大事件です。代表的なのがペストの大流行です。その結果、労働力の大幅な減少をもたらし、小作人をその地域に縛り付ける封建制は崩壊せざるをえなくなりました。その後世界は自由な渡航が可能になり、大航海時代を迎えました。そこで絶対王政の国ポルトガルやスペインが力をつけて、植民地支配をすることで収奪的な政治体制や経済を築き上げていきました。収奪的な制度は様々な軋轢を産み、権力者だけが栄える構図になり、多元的な発展には結び付かないとしています。
それぞれの国が変化する中で、異なった変化をした国がありました。それはイギリスで1688年の名誉革命をきっかけとして、政治経済体制が収奪的な体制から包括的な体制に変わりました。その後イノベーションが起こったのが産業革命です。イギリスも植民地を多く持っていましたが、それらの植民地は、スペインなどの植民地とはやや違い、収奪的ではなく包括的な要素を伴った体制になっていったと考えます。
フランスも絶対王政から1789年のフランス革命を経て、市民の基本的人権を認めた人権宣言が出され、包括的政治経済体制になりました。また、日本についての言及もあります。日本は黒船などの海外からの外圧によって、既存の体制が維持できなくなり、長年続いた封建制が終了しました。権力が移行した明治維新政府は、創造的破壊を推し進めることで包括的な政治経済体制の基盤ができたとしています。
まとめると衰退する国家は、収奪的な体制が変わらない国家であり、一部のエリート層だけが富を搾取する体制を維持しているとしています。その結果、政権の交代があっても次の権力者も富の独占を志向して、悪循環に陥るとしています。
一方で繁栄する国家とは、ある程度の中央集権的なまとまりがあり、自由市場が存在する体制のことを包括的制度との表現を使っています。そのような組織ができると、人々のモチベーションが上がり、イノベーションに対する意識も高まり、好循環が生まれやすくなり繁栄する国家になると考えられます。
4, 明治維新の革命性
二世紀半にわたり安定していた徳川幕府が不安定さを増したのが、ペリーが浦賀に来航するなどの黒船騒動など外圧の激化です。それに呼応して幕府を批判する薩摩藩や長州藩を中心とした倒幕運動に発展していきました。その同時期には清朝(中国)もイギリスによるアヘン戦争の敗北をはじめとした外圧にさらされるようになっていました。アジアが欧米列強に支配された時代です。ベトナムを含むアセアンやインドなどもそのような時期にイギリスやフランスに支配される時期に重なります。
アジアの危機の時期に明治維新は起きました。大政奉還、王政復古という権力の交代が起こりました。ところでこの政権交代である明治維新は、徳川幕府の統治制度を徹底的に壊していきました。政治・社会・法律・経済・文化を徹底的に変えました。版籍奉還、廃藩置県、四民平等、廃刀令、徴兵令、地租改正、屯田兵による北海道開拓、殖産興業、文明開化、学制公布、廃仏毀釈、国会開設、大日本憲法制定など矢継ぎ早に改革を進めました。暦も太陰暦から太陽暦に替えることになりました。全部が成功した、あるいは正しいと評価されているわけではありませんが、その政府は改革に躊躇はありませんでした。
明治維新政府は江戸を東京と改称し、首都として天皇も政府も移りました。幕藩制を完全に廃止して、中央集権国家と資本主義化の基礎を築きました。同時に殖産興業と富国強兵を推し進め、欧米に負けない強い国になる改革を進めました。明治維新のその後は、日清戦争、日露戦争へと進んでいくことになります。
このように明治維新は革命と呼べるような大変化でしたが、イギリスやフランスの革命のように民衆が立ち上がったり、王宮を包囲したりするような民衆が蜂起の中心になった革命ではありませんでした。どちらかというと外圧によって既存の権力が揺らぎ始めたところに、それに批判的な勢力が政権交代を挑んでいった構図であるように思います。その点でいうと、欧米の変化の仕方と日本の変化の仕方はやや異なると思いますが、現在において繁栄している国家とみなされるきっかけは、明治維新の大改革が影響していると思います。
5,政治経済制度はなぜ重要か
冒頭でトランプ大統領の任期が残り4年となっていること、中国、ロシアは憲法や政令を改正して政権トップの在任期間を延長していること、北朝鮮に至っては最高権力者が世襲によって固定化されていることを述べました。米国に関していえば、多少極端な政策をとっても、トップが変わる新陳代謝によって修正は行われるだろうと思います。政権交代が発生しない国にとっては、権力が固定化されて、権力者の力を維持するために制度が固定化されます。
歴史の過程の中では多少の例外もあります。社会主義ソ連が一時期重化学工業の発展や宇宙開発競争で米国を凌駕した時期もありました。しかし、それは、採算性を度外視した軍需産業や宇宙開発競争に引っ張られたものであり、その後起こってくる情報通信革命には対応できませんでした。米国では軍需産業の転用による情報通信革命が民需主導で行われて、創造的破壊ともいえる産業の変化が起こりました。独裁的国家の収奪的な体制では、限界がすぐに訪れると考えられます。1978年改革開放政策に転じて以来、確かな成長を遂げてきた中国も包括的体制にならない限り停滞のリスクはあるでしょう。
確かに現状の資本主義は格差を生み出す仕組みであることは間違いがないけれど、自由な市場経済が誘発する創造的破壊、それによる経済的勝者の交代可能性があることが健全性を高めています。それぞれの国家の選挙制度も、権力の交代可能性を担保されているならば、創造的破壊やイノベーションを産むための基盤が確保できていると言えるでしょう。
頑張れば頑張るほどインセンティブを受け取ることができて、人間の本質的な欲求を満たすことができる制度を守ることができれば、組織は発展の方向性を築くことができるとも考えられます。その一方で個人のインセンティブを組織が吸収し、組織は発展するが、個人の欲求は満たされない組織は停滞することになるとも考えられます。包括的制度とはそれぞれの個人のやりがいや社会的貢献も含めて、個人の意欲や欲求に素直な選択ができる制度と見ることもできます。
これは国家のみならず、企業などの組織についてもいえるのではないかと思います。創造的破壊やイノベーションが起こる組織は、一部のエリートやトップだけが経営権と利益を握っている組織ではなく、社員のモチベーションを高める制度を築いている組織でしょう。その体制を築いた組織は長期的な繁栄を確保できるのでしょう。しかし、組織はトップが長期に固定化し、組織体制が次第に硬直することによって、衰退の道をたどることもあります。「国家はなぜ衰退するのか」は数々の示唆を与えてくれた本でした。
以上