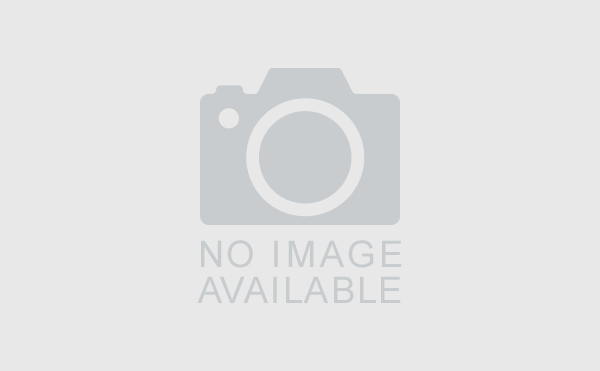構造的経済問題の日本と秩序が急変する世界
1, 参議院選挙争点「減税か給付か」論議の不思議
さて、7月20日に投開票が行われた参議院選挙ですが、衆議院選挙に続いて与党である自公の過半数割れという事態になり、政局が流動化する事態となりました。選挙後も首相の責任問題など混乱が続いています。8月後半にかけて大きな変化があるかもしれません。
ところで私が海外にいながら、選挙戦の様子を垣間見たときに感じた違和感について触れてみたいと思います。それは与党も野党も物価高対策として、減税あるいは国民への給付金の支払いを盛んに訴えていたことです。物価高で国民が困っているところですので、減税をして助ける、あるいは緊急の給付金を出して助けることが悪いというわけではありません。
私が不思議に思うことは、物価高がなぜ起こっているのかの原因についての考察がほとんどされてないことです。物価高の原因を知らなければ、将来にわたり根本的な解決ができません。また、財源が不確かな状態での減税や給付をすることは、将来の借金にあたる国債を増発するしか方法はありません。
さて、物価高の原因とは何なのでしょうか?簡単に言うと輸入品がインフレを引き起こしているからです。国内のコメ不足でコメの価格が急騰したような例外はありますが、主な要因は輸入品が上がっていることです。日本からの輸出品目は自動車、半導体や電子部品などが中心ですが、輸入品は食料品やエネルギーが主なものです。輸入品が上がっているので、食料品の価格が上がっています。また、エネルギー価格が上がっていますので、電気料金や輸送に関するコストも上がっています。
なぜ輸入品の価格が上がっているのでしょうか?その最大の要因は円安がもたらしているのです。海外で生活していると円から外貨に換えること、またその逆で外貨から円に換えることも多いので、為替の変動に関しては日々関心が高くなります。円安の時は外貨から円に換えると得をした気分になりますが、円から外貨に換えると以前に比べて交換できる外貨が安くなります。しかし、日本だけで生活をしていると為替の意識は持たないでしょうから、物価高だけが気になることでしょう。
私は日本の物価高の主要な要因が円安だと考えていますが、円安に至った原因が何なのかをとらえることは、今後の解決策を間違えないためにも重要性が高いと思います。今回は参議院選挙の際に各党が訴えていた減税と給付を行うことがどんな社会に導くのかを考えてみたいと思います。
2,円安になるロジックと近年の経済政策
円安になる要因として重要なのが金融緩和政策でしょう。日銀が国債を大量に買い入れる代わりに、貨幣を印刷して市場に資金を供給します。同時に金利を引き下げて、企業や個人が資金を借りやすくする金融政策です。市場に資金が潤沢に供給され、金利を引き下げることから企業や個人はお金を積極的に借りて、経済を活性化させるのが目的でした。一方で金利の安い円ですから、円を売って金利の高い外貨を買う動きが活発になります。国内経済を活性化されるが、円の価値が相対的に下がります。
しかし、その政策のその当時想定通りに進まなかったのは、日本経済はデフレ経済に陥っていたことでした。市場に資金を供給しても、将来の方がもっと安くなると考えれば、資金は使わないで将来のために残しておこうとします。デフレは今お金を使う気持ちに水を差す状態です。それがデフレ下の日本経済の状況でした。金融緩和にもかかわらず、経済は停滞したままで時間だけが経過しました。長期間の金融緩和が続けられたことから、円安は構造的にさえなってしまいました。その政策の過程で金利を上げることが事実上できなくなっていました。国債を大量に保有している日銀にとって金利を上げることは致命傷になるのです。
円安にはメリットもあります。輸出企業は収益が改善します。今までよりも輸出品目の価格は下がりますが、収益に影響はありません。それ以上に輸出企業の価格競争力が増し、より一層売れるようになります。近年日本では外国人の観光客(インバウンド需要)が拡大しているのも同じロジックです。高い外貨から円に交換し、安い円の商品を購入することで思わぬ為替差益を享受できることになります。
しかし円安のデメリットが日本の家計を悩ませています。述べてきたように輸入品目の価格の上昇を招きますから、エネルギー(石油)や食料品を海外に依存している日本では商品価格が上昇します。一方で外国人の日本観光は増えていますが、日本人の海外旅行は減っています。海外旅行や海外に駐在する日本人も円ベースの資金を利用すると以前に比べ負担が増えることになります。
アベノミクスと称された金融緩和政策は円安のもとで、輸出型の製造業が復活して、日本経済を復活させる側面があったことは否定しません。しかし、金融緩和を長期間継続したことで、日銀は金利を上げる舵は取れません。また、輸出型の製造業で経済を支えられている側面もあるので、円安を脱却する方向には進めません。
言ってみれば金融緩和政策の長期化は、慢性疾患の患者に投薬を続けるしか方法がない状態に陥っている状態と考えることができます。投薬を停止した瞬間に患者は病状が悪化してしまいます。日本経済はまさにそんな状態で、金融緩和という投薬を中止できなくなっているのです。
3,減税や給付を進めると何が起こるのか?
選挙期間中に訴えられていたのは、消費税の減税あるいは廃止、一方で消費税の減税に手を付けてまでも今の国民の生活を守るべきか、あるいは将来の社会保険にも悪影響をもたらすこともある減税ではなく、一時金給付で国民生活を支援するという論議でした。
政府の財源には制約があります。一つは税収を確保して給付する方法です。これをするためには増税が必要となり、現状では誰もが賛成はしないでしょう。もう一つは財源を国債に頼る方法です。国債とは国の発行する債券です。法律で定められた発行根拠に基づいて行われます。国債は利子の支払いと満期時に元本の支払いを約束された債券ですので、国が国債を買ってくれる人たちに借金をしていることになります。現実に国債の発行残高は約1000兆円、地方債が200兆円にも上っているとのことです。
国債の返済方法は、税収が伸びていればその税収で返済する方法はあります。しかし、このような巨額の国債残高を税収で返すことは現実的ではありません。現実的な方法はお金を刷って返済に充てる貨幣鋳造権を行使する方法です。ただ、日本では貨幣発行の権利を持っている日銀が、政府から独立した貨幣の番人として位置づけられています。政府が勝手に貨幣の発行を日銀に命じられないようにしています。
日銀が貨幣の番人という役割があるのは、貨幣鋳造権を安易に使うと、貨幣価値が暴落して急激なハイパーインフレを招くことになるからです。急激なインフレは国民生活を一層の混乱に巻き込むことになります。このようなことを避けるために、国債の返済のためにさらに国債を発行することは、増税をさらに先延ばしする無限ループのような状況になります。その結果はいつかどこかのタイミングでハイパーインフレを招くことになります。将来への先延ばしを避けるためには、地道に税金で返済していく財政の健全化を進めるべきだとの考えがあります。
一方で、国債の発行はあまり心配いらないという意見もあります。一般企業の借金の多寡を分析できる会計学を応用した考え方です。政府の借金総額だけを見るのではなく、政府全体の保有する資産とのバランスに着目すると実質的な借金はかなり縮小するので、心配はいらないという高橋洋一氏の考え方もあります。政府の保有する資産が機動的に活用できるかの問題はありますが、それらの議論には相対的な国際比較は必要でしょう。あまりにも諸外国と違う方法を取っていると、日本だけが沈んでいくことになりかねないと思います。
一概に国債に依存することを否定はしませんが、国の成長による増収が期待できた高度経済成長期ではありません。財政規律を考えない、今だけしか考えない政策をしていたら、ますますの円安をもたらします。選挙戦を通じた論議は、短期的な視点の論議に感じたのは私だけでしょうか?日本は長い歴史の中で、かなり統一的に国の体制を維持してきた珍しい国です。その国で将来の国民のことを考えない政治をしていることは、精神や哲学の劣化をきたしていると考えることができるかもしれません。
4,国際秩序の変化を生む予兆
円安の話をしてきましたが、もう一つの要因はあります。米国の巨大なIT企業が提供するプラットフォームへの外貨支払いによる「デジタル赤字」のことです。急激なIT化の進展により、巨大なプラットフォームを作ったのは、アマゾンやアップルなどの米国のビックテック企業です。それらのサービスを利用する日本人の持っている資金が「デジタル赤字」として海外に富が流れているのです。通信革命の変化に出遅れた日本経済は旧来型の産業に依存していることから、輸出企業に頼らざるを得ない面もあり、円安が国策だという意識から抜けられません。
一方で新しいプラットフォームを作っているのは中国です。中国発の「Tik Tok」を活用したマーケティング戦略がベトナムでも盛んにおこなわれるようになっています。多くの一般ユーザーも活用しています。中国のIT企業の成長は、中国自体は国家資本主義ともいえる体制で、国家主導で新規産業を育成している側面があります。その産業を利用して、新興国に関係性を築こうとしている動きがあります。
新しい産業育成に力を発揮しているのが米国と中国ですが、新しい産業育成にとどまらない国際秩序の変化がじわじわと押し寄せていることを感じています。世界を主導してきた米国が役割を変えようとしているのです。逆に中国は米国が変えようとしている役割を取って代わろうとしているようにも思えます。
米国はトランプ関税を持ち出して、米国が本来進めてきた自由貿易をから保護貿易に舵を切りました。米国が主導してきた世界貿易機関(WTO)の秩序を壊そうとしているように見えます。戦後の国際秩序は、米国を中心とした国際連合による国際政治秩序の形成、ブレトン・ウッズ体制によって築かれました。ブレトン・ウッズ体制はニクソン・ショックで崩れましたが、第二のニクソン・ショック(トランプ・ショックとでもいうのでしょうか)が起こる気配さえ感じます。米国が主導した戦後の貿易決済システムや為替安定の仕組みさえも捨て去ろうとしているように見えます。
それ以外でも米国が離脱を発表しているものが多くあります。世界全体で地球の温暖化を阻止する枠組みである「パリ協定」の離脱、世界保健機関(WHO)からの離脱、ユネスコ(国連教育科学文化機関)からの離脱です。米国の主張に反した対応をしているとの理由から、それらの組織からの離脱を発表しています。米国が国際秩序を維持する役割を放棄しているようにも見えます。
その一方で中国は6月「中国・アフリカ協力フォーラム」を開催して、アフリカ諸国と自由貿易を進めようとしています。6月にはロシアも「サンクトペテルブルグ国際経済フォーラム」を開催しています。また、7月には「BRICS首脳会議」も開催されて、米国抜きの国際連携の動きも進んでいることにも注視が必要です。
トランプ大統領のロシアへの停戦の呼びかけにも、プーチン大統領が無視を続けることができるのも、そのような国際秩序の変化によるもののような気がします。米国が国際秩序の維持に消極的になっていることは明らかになってきました。そのほかの超大国も国際協調を無視するようになったときに何が起こるかを考えると不気味です。国際秩序の在り方が不透明さを増しています。新たな秩序形成のためにどの国がどのように動くのか最近の動きは時代の変化を感じるものです。
5,「虚構としての国家」を支える哲学の変化
人間が動物とは違った進化を遂げた理由として、虚構を作り支配する、あるいは統一する仕組みを生み出したことを上げる歴史学者も多く存在しています。最近では「サピエンス全史」という著書があるユヴァル・ノパ・ハラリ氏が言うところの「認知革命」が有名です。認知革命とは虚構を必要なものとして認知させる力のことを言います。主な虚構としては国家、宗教、貨幣があげられます。これらの虚構によって、人や組織を支配する仕組みが作られます。
国家の歴史からとらえてみると、ある出来事によって虚構が壊れる瞬間があります。ソビエト連邦はベルリンの壁の崩壊などを経て、ソビエト連邦の解体が起こったのが1991年のことです。第二次大戦後には植民地支配が崩壊し、民族自決の哲学がアジアやアフリカの国々を独立に導きました。それにさかのぼる第一次世界大戦後には、中東を支配していたオスマン帝国が崩壊して、今の中東の国々に分かれていきました。いずれにせよそれらの国を維持していた前提となる思想が崩壊したことが理由です。
今では覇権国である米国が独立したのは、1776年ですからたかだか249年前ということになります。移民の国米国は独特の独立宣言により国の哲学を決めて、それによって統一を維持してきました。有名なその独立宣言とは、1776年7月4日に米国の13の植民地がイギリスから独立を宣言したときの文書のことです。トーマス・ジェファーソンが起草して「人間の平等の権利、生命、自由、幸福の追求の権利、そして政府に対する革命権」も主張しました。この宣言はその後の米国を統一する象徴的な宣言になり、建国の精神を象徴する重要な文書になりました。米国の統一を保っているのはこの宣言とも言えます。移民社会の米国はこの理念をもって、他民族の統一を実現したのです。ところがその理念から逸脱するような動きが目立っています。主義主張の分断を招き、国が一つにまとまらなくなっています。
超大国が崩壊した例は、1991年のソビエト連邦の崩壊があります。ソビエト連邦が崩壊した理由は複数の要因がありますが、社会主義の計画経済のもとで経済が停滞して、国民生活が成り立たなくなったこと最大の理由でしょう。国の基本哲学を変えざるを得なくなった結果と考えられるかもしれません。政治体制もソ連共産党の一党独裁は社会の活力を低下させ、官僚主義や腐敗も蔓延していたようです。ソ連は多民族国家であり、各民族の自決を求める動きが強まったことも解体を促進させました。合わせてゴルバチョフ書記長によるペレストロイカやグラスノスチ(情報公開)といった改革を試みましたが、改革は中途半端に終わり、かえって社会を不安定化させてしまった面もあるようです。それによってゴルバチョフ氏は辞任し、ソ連は解体されました。
それ以降のロシアは哲学の変化があったようにも見えます。プーチンのロシアは、国の統一性を「ロシア正教」という宗教をもって保とうとしているように見えます。ロシア正教の歴史をたどるとロシアだけでなく、ウクライナ、ベラルーシにもその影響力が及んでいたことからも、ロシア・ウクライナ戦争は宗教の影響もあるかもしれません。
一方、トルコを含めた中東は第一次世界大戦までオスマン帝国が支配をしていました。第一次世界大戦でドイツ、イタリア、オーストリアと組んだオスマン帝国は、イギリス、フランス、ロシアの連合国軍に敗れて解体することになりました。歴史的には中東から北アフリカを支配していたオスマン帝国ですが、近代化に失敗して挽回を図った第一次世界大戦でも敗北して、領土の大幅な分割を余儀なくされました。従来からの政治体制であったスルタン制やカリフ制という国を維持する仕組みも機能しなくなって、帝国自体が衰退の方向に進んでいました。
そこにトルコ革命が起こり、オスマン帝国は崩壊しました。オスマン帝国崩壊後の中東は、サンクス・ピコ協定によって戦勝国のイギリス、フランスの影響下にある領土を分割されました。現在のシリア、イラク、レバノン、パレスチナのある地域のことです。第二次大戦が終わると、パレスチナの地域にイスラエルが建国されて、現在のガザ問題の要因になっています。今日の中東地域の政治情勢に混迷の要因はオスマン帝国解体の過程で起こったと考えていいように思います。
そのようにここ100年程度の歴史を見ても大国が崩壊することは珍しいことではありません。米国の変化と今後の世界に与える影響は、かなり大きなものになると思えます。もしかしたら歴史の転換点がこの時期から始まったと言われることもあるかもしれません。米国の変化は世界の秩序を変えるきっかけになるかもしれないと思いつつ、歴史とは途方もない変化を生み出す力があることを感じています。人間社会の統一を図っている哲学の変化が、社会の仕組みを変えていることを感じています。虚構である哲学の変化が社会秩序を変えているのです。
以上