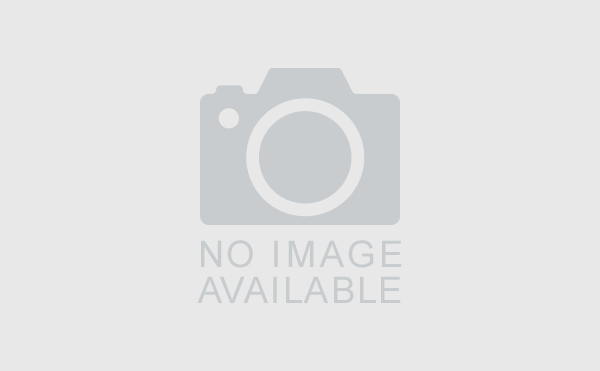「世界の工場」はどこに向かっているのか
1, グローバリゼーションから自国第一主義への変化
1980年代米国共和党のレーガン大統領の時期には、伝統的な保守主義を基盤としていましたが、経済の面では自由貿易の推進や規制緩和という新自由主義思想をもって進めていました。米国の伝統的な保守主義とは、法とキリスト教信仰の維持、西洋文明の防衛と考えればいいのでしょうか。そのような考えに基づいていましたから、中国との自由貿易に関しても否定的ではなく前向きにとらえられていました。2001年ブッシュ(子)政権の際には、中国がWTOに加盟もしてグローバリゼーションの中心に位置づけられるようになったことも、米国の支持や後押しがあったことが一因です。
ところがそれから10年以上経つと、生産拠点が海外の安い工場に移転されており、国内ではモノが生産されていない状況に陥っていました。規制緩和によって米国ではビックテック企業の成長は促進されましたが、その成長によって利益を得られたのは、先端技術の知識を持った人、それらの経営に長けた人、新たな金融手法の知識を持ち資金集めの能力を持った人たちだけでした。そのため中間層が没落していったのです。中間層は社会での役割を持ち、生産に貢献し、自分自身や子どもたちの将来を補償することを求めるささやかな希望を実現しようとしている人たちです。製造業が衰退することで、それらの人たちの基盤が失われていきました。
それらの中間層の崩壊がトランプ政権誕生の要因になったとは思います。大統領に返り咲いたトランプ氏の思惑は、中間層の立て直しと製造業の復活になるのでしょう。トランプ氏が進めようとしている政策は、自国経済の妨げになると考えている貿易の不均衡の解消です。世界の工場が他の地域に移ったことで、工業製品の輸入拡大で米国は貿易赤字に陥っています。その解消を追加関税によって是正しようとしています。他国から輸入される工業製品に高関税をかけて、輸入品の消費が減っている間に米国の製造業を取り戻すと考えているのでしょうか。
それと同時に、安全保障に関する負担も米国経済の足かせになり始めており、安全保障の費用を同盟国側に求めようとしています。貿易同様に考えられており、負担の増額を求めています。この考え方は国と国とが友好関係でつながっているのではなく、自国にとってのみ良いと思われる政策を実行する考え方です。第二次世界大戦後、米国中心に築いてきた公正な競争による国際秩序の維持という考え方とは一線を画します。
自由貿易という考え方を排して、お互いが当分の利益をもたらす国同士としか取引をしないブロック経済的な考え方に基づいていると思われます。貿易赤字を生まない取引に限定して、その間に世界の投資を招き入れて、米国の製造業を呼び戻す政策に転換したものと思います。関税によってそのような成果がもたらされるかはわかりませんが、自由貿易やグローバリゼーションとは逆の回転になり始めたのは事実と思われます。
2,「世界の工場」の移り変わり
「世界の工場」と言われる地域は時代とともに移り変わっています。19世紀は産業革命以降、エネルギー革命や大量生産が可能になったのがイギリスでした。産業革命により先進工業国になりましたが、多くの植民地を持っており、世界中から原材料を輸入して、良質で安価な工業製品を大量生産できるようになりました。それを世界に輸出することで、多くの利益を上げ覇権国と呼ばれるようにもなりました。
20世紀の世界の工場と言われたのは米国です。それには世界大戦の戦禍を免れた地理的な要因もあります。第一次世界大戦はヨーロッパが戦場になりました。そのため生産地は米国に移転し、米国の製造業が急激に伸びました。流れ作業による大量生産モデルは、効率的な生産とコスト削減が同時に実現できるものでした。その方式はヘンリー・フォードによって確立されフォーディズムとも呼ばれました。第二次大戦もヨーロッパや東アジア、東南アジアが戦地になりましたが、米国が戦地になったのが真珠湾だけでした。それらの要因が米国を「世界の工場」と覇権国に押し上げました。
戦争以外に米国が世界の工場になった要因があります。豊富な天然資源や安価な労働力があったことです。米国には鉄鉱石、石炭、石油などの天然資源も豊富にあります。また、移民の流入が安価な労働力確保の要因になりました。米国では20世紀初頭に始まった教育運動があり、教育水準の高い労働力を有する環境が作り出されていました。これらが複合的に作用して米国が「世界の工場」になっていました。
その構図が変化をもたらすのが世界の冷戦構造です。第二次大戦後、発展途上国は民族解放運動から独立に進んでいきました。その思想的基盤には階級闘争のマルクス主義的な思想をも背景にしていました。アジアでは中華人民共和国の誕生、朝鮮戦争の勃発、ベトナム戦争の激化など激しい変化に見舞われました。その中で米国とソ連によるそれぞれの西と東のブロックによる冷戦構造が世界を変えていきました。
西側ブロックの一員であった日本はアジアの共産主義への防波堤として、朝鮮戦争、ベトナム戦争の米軍基地として、資材の調達先として、工業化に進むことを求められていました。日本には豊富な天然資源が足りませんでしたが、それは西側諸国との自由貿易で調達できるものでしたし、安価な労働力と教育された労働力が豊富に存在していました。戦後のベビーブームも相まって人口は着実に増える国になっていました。そのこともあって、20世紀の後半は、「世界の工場」が一時日本に移り始めていた時期でもありました。
20世紀の終盤から21世紀にかけそこで急に台頭したのが中国です。「世界の工場」は中国が取って代わっていきました。中国は1980年以降から、最高指導者に鄧小平が就き、経済開放政策を進めていきました。「黒猫でも白猫でも、鼠を捕るのが良い猫だ」という言葉は有名ですが、実践的な力を蓄えて着実に力をつけていこうとする当時の中国を象徴する言葉と言えるでしょう。中国は外国の企業・工場を積極的に受け入れ、資本や技術力を中国に取り入れる方向を選びました。中国には安くて豊富な労働力があることも有効でした。天然資源も日本に比べても豊富にあることから、「世界の工場」に突き進んでいくことができました。特に鉄鋼、機械、化学、繊維などの工業生産は世界一の生産高になり、「世界の工場」という名称は中国に移動しました。
3,米国の製造業の復活は難しいと思う理由
さて、米国がグローバリゼーションから、自国第一主義へ変化してきていることを述べました。また、トランプ関税により米国での製造業が復活するのでしょうか。私なりに考えてもなかなか難しいと考えられることを述べてみたいと思います。米国は新自由主義経済政策をとることによって、伸びていった産業があります。シリコンバレーに代表されるIT企業の成長、ウォール街に代表される金融ビジネスやフィンテック企業の成長です。その過程で製造業から没落している中間層の崩壊を伴い、格差が拡大していったのが米国の特徴です。
米国はある程度の経済成長が実現されていたこともあり、物価上昇を上回る名目賃金の上昇が実現できていたようです。また、相対的賃金の安い労働力には移民の流入によって労働力確保がされていました。しかし、中間層の労働者には、自分たちの仕事が移民に奪われていると感じて、移民の排斥を訴えるようになっています。製造業の衰退は、安い労働力の国に仕事が奪われていることを感じて、それらの国に高関税をかけることは合理的と考える人もいます。グローバリゼーションによって、衰退を余儀なくされた中間層の叫びがトランプ現象なのでしょう。そのような米国民の感情はある程度は理解できるのですが、製造業が復活は難しいと思えるいくつかの理由を述べてみたいと思います。
第一には、「世界の工場」に復帰するための安い労働力が供給できないことです。賃金上昇も続いている国ですので、今よりも安い賃金の製造業に移ろうとする人たちがいるのでしょうか。また、移民への排斥の方向性も強めていることから、低賃金の労働力は不足してきているでしょう。合わせて、米国の低所得者層は教育にも十分な力を入れられていないと思われます。その点で成長しようという意欲のあるアジアの方が良質な労働力確保には有利なのだと思います。
第二には、高関税にすることにより米国内の物価は上昇することになるでしょう。関税の増額分を価格に転嫁せざるを得なくなることから輸入品は今以上に高くなります。輸入が多いので貿易赤字になっている米国は、当然ですが輸入価格が上昇し、物価も上昇することになるでしょう。そうなると庶民の暮らしを守るために金融当局は金利を上げざるを得ないと思います。その結果、設備投資の金利も上がるため、製造業への巨額の投資は控えざるを得なくなります。高関税の悪循環で、設備投資も難しくなります。金融政策は著しく難しい局面を迎えるように思います。
第三に国際間のサプライチェーンの混乱です。世界各国ともに自国で調達できない素材や部品は海外から調達することで賄っていました。グローバリゼーションにより、それぞれが得意分野の製品を調達しあって、経済を維持していました。それが自国第一主義になることで、従来のサプライチェーンが壊れ始めています。それらの理由を総合的に考えてみると米国の製造業の復活は簡単ではないことがわかります。
4,中国の次に考えられる「世界の工場」はどこか?
「世界の工場」の変遷を見てきたときに、技術革新が起こったこと、戦場ではない地域にあり政治が比較的安定していることなどの要因があることを見てきました。特に重要なのは若くて豊富で安価な労働力があることです。そして教育された労働者がいることが重要な要素であることを見てきました。周辺に天然資源を有していることも踏まえると、候補先は限られてくるように思います。
中国は米国との覇権争いに入っていく中で、中国の「世界の工場」としての地位は以前ほどではなくなることでしょう。世界が中国製品の輸入に慎重になるからです。ただし、米国に排除された国は中国と結びつく現象としてのブロック経済化は進むでしょう。それに対して、米国に製造業が戻るかの論点は後に回すとして、それ以外に考えられる「世界の工場」となる可能性のある地域を考えてみたいと思います。私なりにそこで考えられるのはアジアではないかと思います。
アジアの中で人口が多いのはインドです。インドは中国を抜いて世界一人口の多い国になりました。巨大な内需とIT産業の発展など注目されていますが、インフラの遅れやカースト制度、労働習慣の違いなどインドを取り込むにはハードルが高い面があります。潜在的に力を持っている国であることは間違いないですが、今回の論点は意図的ですが、インドには着目せずそれ以外の国を見ていこうと思います。
重要性を持っているのが、インドと中国に挟まれた東南アジア(ASEAN)諸国です。人口だけでいうとインドネシアが2億7000万人、フィリピンが1億1000万人、ベトナムが1億人となります。それ以外の国ではタイ7000万人、ミャンマー5500万人、マレーシア3300万人、カンボジア1700万人、シンガポール570万人と続きます。それぞれ国の事情が異なりますが、ここでは1億人以上を超えている3ヵ国を中心に考えてみたいと思います。
インドネシア、フィリピン、ベトナムではそれぞれ利点も異なっているかもしれません。豊富で安価な労働力は共通しています。教育に関しては、それぞれ違いがあります。インドネシアは小学校、中学校、高等学校などを卒業するときに国家試験を受ける必要があるようです。ベトナムでは小学校5年間、中学校4年間、高校3年間となっており、小学校、中学校が義務教育です。教育に関しては力を入れており、IT教育も盛んになっています。フィリピンについては13年間の義務教育となっているようで日本よりも4年も長くなっています。また、英語に強いことはフィリピンに優位性を与えています。
それと合わせて「世界の工場」になりうると思われるのが日本です。なぜ日本かというと、日本では「失われた30年」と言われる時期がありました。世界がインフレに進んでいた中で、デフレに進んでいた国だからです。GDPは世界第4位の国でありながら、一人当たりGDPは世界38位まで落ち込んでおり、先進国と言える状況にはありません。「失われた30年」で賃金も物価も上がらなかったことが、復活のチャンスをもたらしていると考えられます。
そんな日本ですから相対的には安価な労働力を確保できる国になりました。合わせてインフラの整備はなされていることから、労働力さえ確保できれば、「世界の工場」になりうるのではと思います。海外からのインバウンド需要が大きく伸びているということは、それだけ魅力的な国ととらえられていることにもなります。若干の労働力の補充があれば産業の成長を実現できる可能性があります。インフラを駆使しなければならない分野、特に装置産業に近い分野で、人海戦術によらない製造業は、日本で得意な分野になるでしょう。私は「世界の工場」になる可能性のあるこれらの国々との国際分業が成り立てば、「世界の上場」になりうるのが、日本を含めた東南アジア周辺国になるのではと思います。
5,国際競争力を取り戻す国家戦略
米国の日本への関税が8月1日より25%とするという書簡が届いたと7月7日に報道されました。日本から米国への輸出の減少が懸念されるところで、日本の経済への影響が懸念されます。しかし、米国が貿易赤字に陥っている理由が、国際競争力が落ちているからにほかならないと思います。例えば日本車が米国で売れて米国車が日本で売れないのは、日本側の需要に米国車が見合わないからです。米国の製品がドイツなどの国の製品に比べても国際競争力が低いからだと思います。米国の製造業は高コストの体質から抜け出せていません。安い部品をメキシコなどの近隣国から調達しても、労働者の賃金が圧倒的に高い状態であれば、高コストからは抜け出せません。そのうえ品質が落ちていれば購入はされないでしょう。
高コスト体質の国際競争力のなさを関税によって解決しようとしています。米国の貿易赤字の原因は、輸入する相手国が公平性を欠いており一方的に悪いと考えているのです。平気で輸出する国を懲らしめるという発想で関税をかけているようにも思えます。しかし、「世界の工場」がイギリスから米国そして中国へと移り変わっていった過程は、各国の製造の方法を学び、安価で豊富な労働者が一生懸命働くことで、国際競争力をつけて、他の国の製品よりも価格や品質向上の努力をしたからだと思います。かつて「世界の工場」と言われた国が復活するためには、再度国際競争力を向上させることに努力するしかないと思います。
日本は「失われた30年」と言われる長期の経済低迷の時期がありました。近年物価が上がり、デフレ経済からインフレ経済になっていますが、物価上昇に比べて賃金上昇が追いついていません。そのため世界の労働力に比べても、安価な労働力が供給できる国となりました。そんな中でアジアは成長し始めており、安い部品調達がしやすいなど日本は地理的要因に恵まれていると思えます。
米国の関税政策で米国の製造業が復活するとは思えません。国際情勢の変化の中で日本がアジアにあることと、アジアの諸国と良い関係性を築くことができるかが重要になっています。市場としても人口の多い地域を相手にできて、米国への輸出減少もカバーできるのではと思います。そのような点で今後はアジア諸国との連携は重要な成長要因になるものと思います。国際競争力をどのようにつけていくか、日本の課題はそこにあるのではと思います。
その当時も貿易赤字に苦しんでいた米国を助けるために結ばれた「プラザ合意」(1985年)をきっかけに大変化がありました。それ以降の急激な円高が発生したことは、輸出で成り立っていた製造業に大きな影響をもたらしました。日本政府は輸出事業者や製造業者を救済するための金融緩和政策を実施しましたが、それにより実業より財テクに走る企業や人々が増えてバブルが発生しました。日本の「失われた30年」は、そのバブルが崩壊したことがきっかけでした。
それにより世界でも類を見ない長期低迷に陥った日本です。そう考えると低迷が長かった分、夜明けの可能性は高いのではと思います。今回のトランプ関税は、今までの国際秩序の変化をもたらす可能性があります。変化を促す要因がある中で、方向性の判断が重要です。日本もそうですが、成長しようとする意欲のあるアジア諸国の周辺に位置していることは、それらのエネルギーを取り入れられやすい可能性があります。外国人に対する扱いが、参議院選挙の争点にもなっています。近隣の国と協力できる関係構築は、日本の成長にも必要な要因であることを思います。上手な外国人との共生を模索していくことは、考えておくべき課題と言えるでしょう。
以上