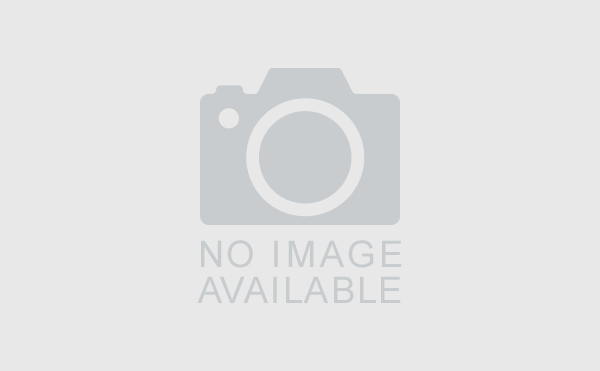戦後日本の成長、失速の要因と時代の転換点を考える
1, 日本の電機メーカーの凋落はなぜ起こったのか
先日、ヤフーニュースを目にしていたら、日本の電機メーカーの世界市場での凋落の記事が出ていました。私が初めてベトナムに来た2007年ですが、それ以降でもまだ日本メーカーの電気製品はあちこちで見ることができました。しかし、今やあまり目にする機会もありません。多くは中国や韓国のメーカーに押されています。ベトナムではスマートフォンも以前はソニーのエクスペディアの販売はされていましたが、今ではアップル以外では中国と韓国メーカーの製品ばかりになっています。
日本の電機メーカーが成長を始めたのは1950年代からでした。1955年以降のラジオの輸出急増、1961年トランジスタテレビの生産開始、1960年代の後半からはカラーテレビの輸出増加など日本の電機産業は大きく躍進をしていました。この成功を後押ししたのが、政府の支援である通産省(現 経済産業省)による産業政策、長期的な視点での投資を可能にした金融システムが企業の成長を後押ししました。合わせて人材が終身雇用制度の下で、高い技術力を持つ人材を長期的に育成することに成功しました。国際環境の中でもアメリカからの技術移転、成長する世界市場、相対的に安価の労働力など有利な条件が重なっていました。
転換点になったのが1985年の9月にニューヨークのプラザホテルで開かれた先進5か国の蔵相・中央銀行総裁会議(G5)において、いわゆる「プラザ合意」が成立したことです。この合意により急激な円高進行が起こりました。1ドル240円程度だったのが、1年後150円程度まで円高が進みました。そのことにより日本製品の価格上昇により、競争力が低下してしまいました。同時に貿易摩擦も深刻化して、半導体分野では日米半導体協定という日本市場で海外製品の利用の義務、米国への輸出の制限など不利な協定を締結せざるを得なくなりました。
この時に日本政府が取った策は、円高不況を解消するための金融緩和策でした。それがバブル経済を引き起こすことになりました。多くの電機メーカーは金融緩和により、積極的な設備投資や人材採用をした結果、その直後のバブル崩壊によって思い負債を抱えることになりました。
しかし、日本の電機メーカーが競争力を失っていった背景には3つの主要な要因があることが分析されています。一つが過剰品質へのこだわりです。「品質」を重視するあまり、市場のニーズとのミスマッチを起こしてしまいました。また、日本では25年保証というようなDRAM(半導体メモリ)を開発しましたが、数年もてばいい製品に対して過剰な品質のこだわりが、価格競争力を失うことになりました。テレビ事業では画質への過度なこだわりが、コスト高を招くことになり競争力を失いました。アナログからデジタルに移行する中で、従来の品質の差が見えにくくなり、新興国メーカーとの価格競争に負けてしまったのが大きな要因です。
2,戦後日本が復興・成長できた理由
さて、日本の戦後の経済成長について考えてみることにしましょう。日本の戦後は連合国による日本の管理(占領政策)から始まっています。当初は日本を非武装かつ民主化し、アメリカや連合国の脅威にならないための政策を実行されました。その中で五大改革指令というのがあります。幣原内閣の時期ですが、GHQが出したこの改革はほとんど実行に移され、ある意味で戦後日本復興の土台を作っていきました。
- 女性参政権の付与
- 労働組合の結成奨励
- 教育の自由主義的改革
- 秘密警察などの廃止
- 経済機構の民主化
しかしながら、日本が高度経済成長のきっかけを作ることができたのは、国際政治の変化によるところが大きかったと思います。いわゆる「冷戦体制」の形成がこの時期から始まったことです。
この間にアジアで起こったことが、日本にプラスを呼び込みました。1949年中華人民共和国の成立です。毛沢東率いる中国共産党が、蒋介石率いる国民党に勝利して中国本土を支配する勢力になりました。蒋介石らは台湾に移動して中華民国として、1971年まで国際政治上は中国を代表していました。もう一つの出来事は1951年から1953年まで朝鮮戦争が勃発しました。この戦争で特需景気が起こったことで、トヨタ自動車など今も日本を代表する企業が成長することができました。
それらの変化を受けて、米国はトルーマン・ドクトリンとして共産主義の封じ込め政策に移行していきました。この政策によって日本を西側に取り込む力学が働き、米国からの投資も本来蒋介石の中華民国に向かうはずか、日本に向かうことになりました。戦後日本の高度成長に礎にはこのような国際政治の急激な変化にありました。
また、この時代は英国の首相であったチャーチルの「鉄のカーテン」という表現が有名です。この言葉にはソ連の影響下にあった東ヨーロッパと西ヨーロッパに分断されて、東ヨーロッパがソ連の支配下にあることを表した言葉です。そのような国際環境の中で、日本はその当時国際政治の主導権を取っていた米国の多国間協調政策の受益者としての立場を築くことができたのです。
日本に訪れた内部要因も経済の好転には寄与しました。団塊の世代と言われる世代の誕生です。1945年には7200万人だった人口が、2008年には12,800万人にまで増えていくきっかけの人口爆発が、この団塊世代が誕生した時期からでした。同時に敗戦後に日本人の給与水準も安く抑えられ、安価な労働力がありました。戦時下の統制経済を継承された官民複合体や石炭・鉄鋼への投資を進める傾斜方式も経済の復興には寄与しました。その当時米ドルと日本円は、1ドル=360円と決められたドッジ・ラインも、経済の安定的成長への基盤になりました。
3,冷戦終結後の日本の失速の原因は何か
さて1989年ベルリンの壁の崩壊以降、1991年にソ連が解体されるなど冷戦構造が終焉を迎えました。1993年にはヨーロッパ各国がEU(ヨーロッパ連合)を発足して新たな時代を迎えました。1997年には香港が中国に返還されて、中国の影響力も一層増していきました。
冷戦終焉後の世界を語るときに、中国の台頭を抜きにしては語れません。世界の工場が中国に移動していく段階です。同時に中国周辺国、あるいはアジア諸国が成長を始める時期を迎えたのです。雁行形態論という言葉がありますが、後進国の産業が先進国の産業をキャッチアップすることを表す言葉です。まずは製品を輸入することから始まり、その後国内生産をするようになります。最終的には海外に輸出もできるようになります。日本が成功体験に浸っている間に、技術力や競争力をつけ、先を行っていた日本を追い抜いてアジア諸国が成長できるきっかけをつかんだのです。日本の成長の時もそうでしたが、安い労働力と豊富な人口があったからです。
一方で米国は冷戦下の西側の中心という地位が徐々に厳しくなっていきます。冷戦後、米国が「世界の警察」として管理する役割を期待されていましたが、余力はだんだん失われていきました。この間、米国では2001年同時多発テロに遭遇しました。その後、テロ国家の撲滅を旗印にイラク戦争を行いました。2008年にはリーマンショックも発生して、米国の世界に関する圧倒的な力を発揮することができなくなっていることを感じさせるようになりました。日本の場合、米国に過剰依存をしていることで、米国の停滞とともに日本が衰退をしていることも考えられます。米国では経済は好調なものの、錆びた工業地帯(ラストベルト)と言われる製造業の衰退の反面、金融やデジタル産業の肥大化が進み貧富の格差や社会の分断が起こり始めています。米国経済には光と影が漂い始めているように思います。
この間日本は、冷戦構造の恩恵も失い、アジアの急伸に押されて、製造業も労働力の安い地域に移動していきました。同時に成長の希望を失う中で、向上心と創造力も失っていったように感じます。想像力や革新性を生むための教育システムが十分でないことも考えられます。みんなが同じ勉強をする時代は大量生産・大量消費の社会ではよかったものが、それが時代に合わなくなっていることも感じます。
国も経済政策も既得権益が温存され、新しい技術やビジネスモデルへの展開ができないのも要因です。技術革新や人材育成よりも、補助金による産業育成や長期間の金融緩和や財政出動など安易な給付を続けることで、結果的にゾンビ企業を継続させた政策も問題があったかもしれません。そのような官民ともに将来の希望を失い、活力を失ったことが大きな要因かと思います。その間日本は東日本大震災や少子高齢化の進展など社会の成長に厳しい現実がのしかかってきたことも影響しています。
4,時代が生む民主主義の衰退化
戦後30年を経て世界の冷戦が終結し、冷戦終結後の30年はアジア諸国の成長と米国の世界への影響力が減退しているのを感じさせる時代でした。そして現代はデジタル化やAIなどの技術革新が進んでいます。先進国が少子高齢化に進む中、新興国は人口が増えています。地球環境の変化も叫ばれる中で、新しい社会の構築を求める声も広がっています。
では現代社会はどんな方向に進んでいるのでしょうか。巷で出てくる話をまとめてみると、民主主義の衰退の可能性が伝えられています。スウェーデンの独立調査機関V-Dem研究所が発表した2025年版の「民主主義レポート」によると、調査対象179か国・地域のうちで民主主義陣営は2024年の時点で88と前年より3減り、強権的な権威主義陣営の91を下回ったとされています。欧州のキプロス、スロバキアなど7か国の専制化が進んでいるとしています。
民主主義指数が最も高いのはデンマーク、エストニア、スイス、スウェーデンと続き、日本は3ランク上昇の27位になったとされています。ただ、自由民主主義の体制下に住む人口は過去50年で最小の12%にとどまり、世界の約72%の人々が権威主義体制の統治する国家で生活している状況とされています。世界は日本の現状とはかけ離れていることをあらためて思いました。
しかし、近年の傾向で民主主義が危機と言われる大きな要因は、民主主義陣営の旗手である米国の変貌にあると言えるでしょう。なぜ米国が民主主義の衰退と言える状況になっているのでしょうか?民主主義の衰退の論議の中で必ず出てくる言葉があります。それはポピュリズムの台頭という言葉です。近年急速に普及し、人々の生活に影響を与えているのがSNSです。SNSやインターネットを通じた一部政治家の行動が、エリート層への不満や民衆感情を煽る手法として活用されているのです。国際的な民主主義のモデルであった米国の現状が、民主主義の影響力の低下の要因になっている可能性があります。しかし、この現象は米国に限ったことではなく、欧州でもそろそろ日本にも起こっている現象と言われています。
政治的にも経済的にも中間層が崩壊していく過程で、貧富の格差拡大、政治的にも左右の分極化が進むことにもなり、対立が先鋭化していると言えるでしょう。人々が不満を抱える中で、既存の政治制度への信頼感が低下しています。三権分立(立法権、行政権、司法権)、選挙制度など民主主義の基本が揺らいでいます。権力へのチェック機能が低下すると民主主義の根幹が崩れていくことも考えられます。ポピュリズムの台頭による影響は、暴力行為の容認、排外主義の容認など、人の対立を煽ることで一層の分断を深めることになります。
社会の変化にはそのほかの思想の変化も顕著です。自由な競争により経済成長を図ってきた新自由主義的な経済活動とグローバル経済化が、トランプ関税などの影響で変わろうともしています。反グローバリズムは、自国第一主義や経済のブロック化を生んでいきます。WTO(世界貿易機関)が支えてきた自由貿易の概念が、その中心の存在であった米国によって変えられつつあります。そのような時代の分岐点にどう向き合っていくべきなのでしょうか。
5,選ばれ易い国日本
冒頭では日本企業、特に電機メーカーの凋落の話をしてきました。世界経済に与える日本経済の影響力も大きく低下しています。そこで私なりに考えると、日本人の価値観の転換が求められているのではないかとも思います。日本では高度成長期には大量生産・大量消費の思想に染まっていました。その思想はみんなで同じ方向に進めば大丈夫という発想を生みました。
同時に戦後日本は工業化に成功したことで貿易などの利便性の良い太平洋ベルト地帯が形成されました。京浜工業地帯、中京工業地帯、阪神工業地帯をはじめ、瀬戸内、北九州にも工業地帯が形成されました。その工業化の成功でサービス業も太平洋ベルト地帯を中心に発展していきました。その間人口が都市部に集中して太平洋ベルト地帯以外は、地域の中心都市を除いて衰退していきました。特に第一次産業に携わる人が徐々に縮小し、後継者もいなくなっているのが現状です。その結果、カロリーベースの食料自給率は38%にまで減少し、輸出に頼らざるをえなくなっています。円安の影響もあり食料品の価格が高騰しました。また、別の要因ですがコメ不足に陥ることも増えています。食料安全保障の観点からも農業の再生は避けては通れないことと思います。
日本は美しい自然や長年培ってきた文化や歴史的遺産の豊富な国です。それらの価値を再発見して、世界が憧れる国にすることで新しい時代のきっかけを作れるのではと思っています。海外で暮らしていると日本の社会インフラは格別に充実していることを感じます。また、医療保険や年金制度など生活に欠かせない制度も充実しています。
私は2008年からベトナムに住んでいて、日本の住民票を外していました。しかし、勤務している会社の健康保険が2024年12月から1年間利用が延長されましたが、11月末で終了することになってしまいます。そのこともあり住民票を日本に戻しました。健康保険をマイナンバーカードに付帯されるためです。日本の医療保険制度を失うことは、マイナスの面が大きいと感じたのです。私はたまたま17年以上ベトナムにおります。会社を経営している責任もあり、すぐには日本に戻ることはできません。しかし、日本での生活はよい面がたくさんあると思います。
農業の復活と自然や文化を守ることに力点を置いた政策を推進することで、海外の人々が憧れる国に再構築できるのではと思います。今の日本はエッセンシャルワークを外国人に頼らざるを得ない状況にもなりました。しかし、上手に外国人の活用をすることで、産業構造の転換や日本経済の再生につながるのではと思います。
日本が戦後高度成長したことも、逆に冷戦終結後済停滞したことありました。それには海外の政治情勢の変化、地政学的な状況の変化が密接に影響していました。現在の国際社会は米中の新冷戦、アジア諸国の成長など今までとは異なる変化を生んでいます。その状況のなかでどのような方向性を取るかによって、「失われた30年」とは異なる変化の分岐点を迎えているように思います。ここ30年間以上の冷戦終結後以降世界は成長しました。その時に成長が停滞した日本は、民主的で安全な国であることもあり、インバウンドの急増を見るように、結果的に投資も含めて選ばれ易い国になっているのです。
以上