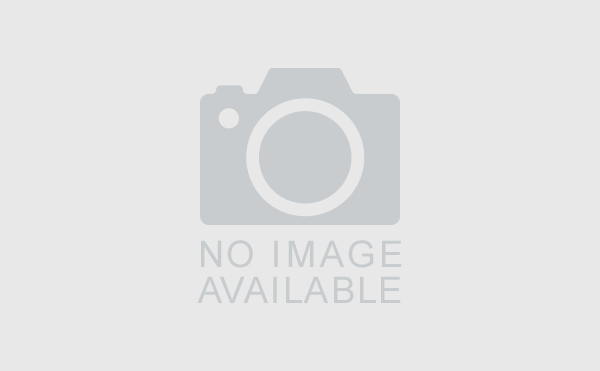AIの進歩から考える新しい時代の居住場所
1, AIの進化は社会をどう変えるか
私の友人のIT会社社長が、「ベトナム・オフショア開発最新情報」というメールマガジンを出しています。9月末に出された記事には、これからの社会の変化に考えさせられる内容がありました。その社長がAIに尋ねる形式で話が進んでいますので、一部紹介させていただきます。
「AIの進化はオフショア開発に影響を与えますか?」という問いにAIは答えます。「オフショア開発に大きな影響を与えます。単純作業の多くが自動化され、オフショア開発のコスト削減のメリットが小さくなります。」さらに続けてAIが答えます。「でも悲観することはありません。AIの進化は変化をもたらしますが、同時に新しいチャンスも生み出します。」自身の事業の縮小を心配する社長の問いに、さらにAIは答えます。「オフショア開発とAIは十分共存できます。AIを活用することで競争力を高めるチャンスです。」
その書かれた内容からAIの洞察力のすごさが伝わってきます。時代はAIを利用することが、効率化をもたらすのは間違いないでしょう。そのメールマガジンを読んで、AIが急速に社会を変えるという実感を持ちました。私がベトナムで行っている事業も、属人的なコンサルティング事業、不動産事業や企業サポートを行っています。これらの分野もデジタル化やAIの活用拡大で変わっていくことでしょう。
AIがもたらすだろう社会の変化について考えてみましょう。AIを利用することで人件費の削減が可能になります。そのことは雇用の喪失を意味します。一方でAIを活用することで、共存できる新しい仕事が生まれる可能性があります。労働時間が短縮し、趣味や人間的な活動に時間を割くことができる可能性もあります。しかし、今までの固定的な業務しか考えられないと、新しい創造的な仕事や趣味は見つけられない人もいるように思えます。
AIの活用は医療にも生かされて、疾病の早期発見なども可能になるようです。また、輸送に関しても自動運転技術の進歩で変わっていくことが期待されています。しかしながら、AIを使いこなせる人とそうでない人では、格差が拡大することが考えられます。新自由主義経済化で所得格差が拡がっていることが問題視されていますが、さらにAI活用でそれが拡大すると一層の社会問題になる可能性もあるでしょう。
また、AIが導き出した結論が、社会的に正しいか、倫理的に正しいかは人間が判断をするしかありません。また、著作権など知的財産の侵害につながる問題も出てくるでしょう。AIに頼りすぎることで新しい問題が生まれる可能性はあるでしょう。AIを上手に活用して、AIでは補充できない創造性や感受性を生かした人間活用、エッセンシャルな業務で自らの役割を果たしていく時代になっていることを感じます。
2,AIに代替される可能性がある職業
AIの普及によってなくなりそうな仕事とはどのような仕事でしょうか。定型的な作業やデータ処理が中心となるような業務は、AIに任せた方が効率的になりそうです。AIは過去のデータの蓄積によって処理を進める装置ですから、新しい発想を生み出すわけではありません。その点でいえば、人間がすべきことはより、創造的で複雑な業務に特化していくことになると思います。または人間相手のコミュニケーションや共感力が必要となる業務も、AIに任せられる仕事ではないようです。
AIに代替される可能性がある業務を取り上げてみましょう。事務作業に代表されるようなデータ処理、書類作成などのルーティン化された業務、決められた手順を反復して行う工場作業、店舗のレジはすでに無人化が進んでいます。将来自動運転が普及していくと、車の運転手もなくなる職業になるかもしれません。ものを書くのは創造的な仕事ですが、翻訳はAIで十分可能になると言えるでしょう。
それに対してAIには代替できない仕事もあります。高度な専門性や創造性を発揮する職業や人間を相手にして共感力やコミュニケーション能力を必要とする業務も残っていくことでしょう。一部装置を利用したほうが便利なものもありますが、人間の手先の器用さや体力を必要とする業務も全部を機械化することは難しいでしょう。
そのように考えると今後人間がAIを使うこと、言い換えれば協業することは必要な能力にはなっていくものと思います。そのうえでAIを使いこなしながらも、AIが苦手とする分野の業務スキルを訓練し、付加価値の高い業務ができるようになることが必要に思います。その点でこれからの人材は、専門性の向上の努力を行い、創造性を発揮して新しいアイデアを考えられることが求められてくると思います。人間社会で仕事を行うなら、コミュニケーション能力と人間への共感力が一層必要になってくることでしょう。
その点でいうと子供が家でゲームばかりをやっていること、友達を作ることが苦手な場合は、これから必要となる能力を育成できないということになります。その点で教育の在り方も再検討が必要になっていると言えるでしょう。ネット社会で自分の興味や関心のあることのみを検索して、自分と意見の合う人だけの接点しか持てないと、人間社会で生きていくことが難しくなることも考えられます。時代の転換点で、どんな教育が必要かも問われる時代になっていることでしょう。
3,米国で起こっている人員削減の動き
2023年ごろから米国のIT企業を中心に大規模な人員削減(レイオフ)が行われていることが伝えられています。2024年はリーマンショック後の2009年のリストラを超えたとの報道もありました。人員削減の理由としては、組織の再編成、コスト削減が主な理由として挙げられていますが、景気後退への備えという回答もあります。米国ではそろそろ景気後退を意識している経営者が多いのでしょう。
従来は業績好調の企業が失業者を吸収していましたが、削減した人員の補充をAIによって進めるとの回答も増えています。社員からAIに置き換えるというと社会的批判を浴びる可能性もあるので、その理由は隠したうえで社員を補充しない企業も多いことでしょう。
主要企業の人員削減を見ていくと米国のビッグテックと言われる有力なIT企業も多いようです。アップルを除くビッグテック企業は、2023年以降大幅な人員削減を行っていることが報道されています。グーグルでは新たな生成AIを既存事業に組み込むためにエンジニアリングや広告部門の人員削減も行っています。メタはマネージャーを管理するマネージャーを削減したほか、テクニカルプログラムマネージャーも削減していると伝えられています。アマゾンも2023年から史上最多の人員削減をしたことが伝えられる事態になっています。
ソフトウェアだけでなくハードウェア分野、eコマース、金融にまで人員削減が及んでいます。大手企業が次々と人員削減をしており、失業者の再就職は厳しい状態になっているとされます。グーグルを解雇された人などは、フリーランスやパートタイムの仕事で何とか食いつないでいると書かれた記事もありました。特に外国人労働者は2か月以内に新たな企業を見つけなければ、就労ビザ(H1-B)の期限が切れるのでとりあえずなんでもいいから就職先を探している人も多いともいわれています。
再就職の競争が厳しくIT業界で働きたくてもできない人が、以前は小規模のIT会社に就職できていました。ところが現在はそれもかなわず、IT以外の再就職先を選ばざるを得ない人も多いようです。ビッグテック企業がひしめく米国で、IT技術者の失業が増えているということは、他の国にも波及していくだろうことは想像がつきます。
あちこちの国で史上最高の株高に向かっている現代社会ですが、その要因の一つが金融政策の影響もあります。どの国もコロナ禍で行われた企業や個人の救済のために金融緩和策を行いました。マネーがジャブジャブにあふれており、世界インフレの原因にもなっています。そのようなインフレ下の安全資産と言われる株式にマネーが流れているのでしょう。しかし、それだけの理由で株高が続くとしたら、バブルはいつか崩壊する可能性もあります。米国で失業者が増え始めている現実は、危険な予兆を感じないわけではありません。
4,「レジリエンスの時代」(ジェレミー・リフキン著)を読んで
レジリエンスという言葉は、困難な状況に直面したときにしなやかに適応して素早く回復できる能力を表す単語です。AIは与える変化がこれからの時代にどんな変化をもたらすか、関心があったのでこの著作を読んでみました。
著者は現代社会を「進歩の時代」と表現していますが、今後は「レジリエンスの時代」に代わっていくと言います。進歩自体は悪くなさそうだが、それに伴う弊害が大きすぎると著者は述べています。無駄を排除し、効率を向上させることで社会は脆弱になっていきました。人間は他の生物と違い、自然を支配できる存在と勘違いをしました。自然を支配し、自らのために利用して、欲望を満たすために利用してきました。新しいモノやサービスを生み出し続ける進歩の時代の考え方が、地球から収奪を繰り返し、地球温暖化や生態系の崩壊をもたらしたと考えます。その結果として、六度目の大量絶滅の危機に向かう可能性を否定していません。
効率の追求と収奪支配から、地球やそのほかの自然を回復させてしなやかに生きる時代、「レジリエンス」に満ちた適応と共存へのパラダイムシフトが必要だとしています。レジリエンスとは元の状態に戻る能力ではなく、新しい水準で適応し自分の居場所を確立する能力を意味しています。
その理由としても、私たちの体を生成している分子や原子は絶えず入れ替わっています。そのため新しいものを取り入れて柔軟に適応しているのが人間であり、生命であるとしています。人体には膨大な微生物が存在しています。それはまさに自然との共生の場です。地球は自転や公転による運動をしていますから、電磁場の影響もうけています。生きているために体内時計も備わっています。人間の存在そのものが自然と共存している生物なのです。
レジリエンス時代に移行する要因として以下のものを上げています。
- インフラの発展 インターネットや流通システムエネルギーシステムの発展
- 人間が持っている適応能力
- 人間が持っている共感能力
- 若い世代の新しい時代の担い手であることの意識改革
著者は経済学、社会学、歴史学だけでなくニュートン力学、熱力学、哲学、生物学、人類学、地球物理学、心理学にも考察が及び、ボリュームのある書籍でしたが、難解というわけではなく、読みごたえはあるものでした。
5,社会が変わることで居住する場所が変わる
AIの進化から論を進めながら、社会は進歩の時代ではなく、レジリエンス(適応し回復する力)の時代に代わっていくだろうと説く書籍も紹介しました。しかし社会は順調に進んでいるときに変化することはありません。今までの日本の変化も外圧が影響していました。徳川幕府の時代が変わったのは、黒船に代表される欧米列強の外圧がきっかけでした。第二次世界大戦に敗北した日本はほぼゼロから新しい時代を作るしかありませんでした。連合軍の占領政策から世界が冷戦構造に進む中で、その世界の変化が日本の復興する力になり、空前の経済成長を遂げました。
現生人類(ホモサピエンス)の歴史を振り返ってもいくつかの環境の変化を伴う革命的な変化がありました。これは外圧というよりは、地球環境の変化、人間が生み出した思想の劇的な変化に負うところが大きいのです。地球環境の変化も重要な要因ですし、停滞した社会への既存の為政者への不満からに起因する世界観の変化が、社会の劇的な変化に影響を与えていると考えられます。
約20万年前に現生人類はアフリカで誕生しました。長く狩猟採集の生活が続きましたが、その地球環境の変化は避けられないものでした。狩猟採集が中心の時代は、生活の食料や資源を求めて各地へ移動していきました。その結果地球上のあちこちに人類が分散していきました。
その後、農業革命が起こり作物の栽培と家畜化が始まったことで、定住生活が始まりました。移動生活に比べて安定した生活が可能でした。そこに土地を所有するという概念も生まれました。定住したその土地を守るために軍隊組織も必要になり、国家という概念が生まれました。土地を侵略者から守ることが欠かせないことになりました。日本でも小国が乱立しながら、次第に力の強い勢力が支配する土地を拡大していきましたが、世界中でそのようなことが起こりました。
海運力のある国が大航海時代の覇権国になり、それらの国が植民地支配できるようになりました。離れた地域でも軍事力を使って支配できましたが、その力が増すことで支配する範囲が拡大しました。その時代には資本主義の概念や保険の概念が生まれましたが、投資をすることで安い原材料を本国に輸送して、技術革新も進み大量生産できる仕組みが作られました。その変化が産業革命を進めることになりました。それにより人口の大都市への集中が必要となり、農村からの人口流入につながりました。
そして現代社会を大きく変えたのが、情報革命という流れになるでしょう。情報革命は、知的労働を拡大し、グローバル接続がグローバル経済の拡大につながりました。インターネットの普及やAIの誕生のどこまでが情報革命ととらえるかの判断は専門家に任せますが、そのことを基盤として住む場所や生活が変わることが予想されます。世界どこにいても対応可能なことから、最適な場所で製造すること、経営することが進み企業のグローバル化が進みました。
これらの変化から世界各地で都市への人口集中が環境問題を生みました。また、行き過ぎたグローバル経済の発展が、自国第一主義のようなポピュリズムを生む背景になりました。地球環境の変化で災害の発生も増えましたし、地球自体のマグマや太陽エネルギーによって絶えず変化しています。巨大な地震などは避けられないでしょう。
このような産業革命、情報革命の急激な変化の中で、人間中心社会の行き過ぎを是正しようという考えが出てきました。医師で作家の養老孟司氏は、「現代の参勤交代」を提案しています。従来の「参勤交代」は徳川幕府三代将軍の家光が行った政策で、
大名に参勤交代を義務付けることで、参勤交代制度を法制化しました。これは大名の統制を強化し、幕府への反乱を防ぐ目的があり、妻子を人質として江戸に置くことも義務付けられたものです。
養老孟司氏が唱える「現代の参勤交代」とは、定住箇所を二か所にすることの提案です。都会と田舎での生活を交互に繰り返すことです。インターネットの普及から都市部と地方の生活を交互に繰り返すことが可能になりました。二か所に定住する生活の意味は、自然と共生するか時間を持つことで現代的な病である「鬱」の解決法にもなるというのです。
また、来るべき大地震や自然災害に備えて、避難場所を作っておく意味もあるとされています。田舎に住むことで「市民農園」のようなものを作り、農作業に慣れていくことが食料不足になった時の保険になることも考えられます。何よりも身体を動かすことで健康の維持だけでなく、心の健康にも寄与するでしょう。私が生まれた長野県は健康寿命が全国一位の地域です。農業県ですので身体を動かすことが習慣化しており、地域の人たちとコミュニティーが維持されていることが、健康で長く働ける要因と考えられます。
家を二か所に持つことは結構お金がかかると思われがちです。しかし、地方で買える家は空き家が増えていることにも関連して、都会で考えるのとは想像できないくらい安く買えるのです。各地方では地域の特性を示して移住者を増やそうとしています。農業革命、産業革命、情報革命という変化の中で、都会と田舎の二重生活をすることは案外人間にとって正しい選択になるかもしれません。
新しい投資の方向として田舎に二拠点生活の家を持つことが、人口の大都市集中を抑制して地方の発展にも寄与することで、国土の保全も図られるのではないかとも思います。人間は生物である以上、自然とのかかわりや人間同士のかかわりが必要です。二か所の居住場所を持つことは、来るべき時代の生き方になるかもしれません。
以上