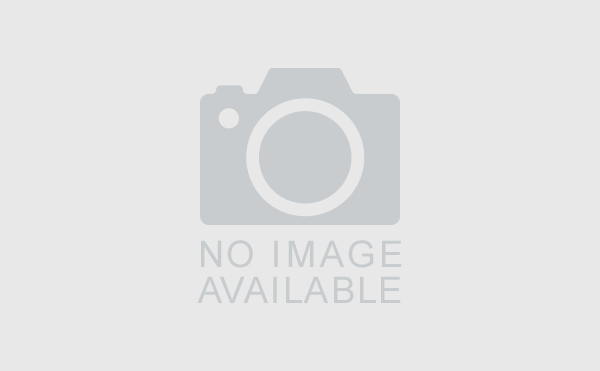PC故障で閃いた現代哲学の変化と管理社会
1,PCのフリーズと高齢化する私の限界
3月1日土曜日はメールマガジンの作成やブログの作成のため、午前中は出勤して作業する癖がついています。この日も8時から作業を開始して、3月3日配信予定のメールマガジンの最終チェックをしていました。メールマガジン配信の担当している弊社のスタッフにメールを送信してしばらくたつと、PCがフリーズして動かなくなりました。最初はマウスの機能の故障かと思い取り替えてみましたが変わりません。PC自体の問題だと気が付きました。
その日は諦めて次の日に来ても状況に変わりがないことを確認しました。仕方ないので、親しくしているIT企業の社長に相談をしました。PC自体も直すのは困難なので、別のPCにデータやソフトの移管を行ってもらいましたが、IDやパスワードの管理を曖昧にしている私では対応ができません。できる人の力を借りないと何も進まないのが現実です。
忙しくしているIT会社社長の好意で電子メールの設定、セキュリティーソフト、オフィスOAソフトの移行をしてもらいました。各種データもクラウド上に保管する、USBメモリーなどに別途保管していればよかったものの、PC故障を想定していないIT素人は、事前の準備を怠っていました。このようなことになって感じるのは、時代は急激に変化しており、新しい技術を受入れることが困難になってきている自分の存在です。
以前スマートフォンをなくした際も同様でした。データが保管されているものを抽出して、新しいスマートフォンに再登録してもらいました。PCやスマホは大変便利ですし、SNSを利用した人とのつながり、PCには作成した書類やセミナーで使う資料など電子的に保管されていることで再利用が可能で、実務の簡便さを与えてくれます。
その技術の進歩のおかげで、時代が変化していることを感じます。私の若かったころの発信の主力は、新聞や雑誌、本の出版、テレビなどへの出演でした。そのためエリートや芸能人など選ばれた人が発信をして、普通の人はそれに影響されて、支持する時代でした。発信するのは知識人や芸能人が中心であり、一般大衆は受け手でした。ところが情報技術の進歩により、いつでもどこでもだれとでも繋がれるようになってからは、発信しようと思う人は誰でも自由に発信できます。
2,急速に変化するインターネット、通信機器の進化
それにしてもPCがなければ、身体を使う現場作業以外の事務的作業はできなくなっています。営業活動もPCや通信機器が重要アイテムです。私の体験上変化した実感があるのは、営業活動にポケベルを使うようになってからでしょうか?1980年に保険会社に入社した私は会社の各部署の見学の中で大型コンピュータが多数置かれたシステム部を見学した記憶がありますが、自分の業務では身近なものではありませんでした。
インターネットの原型が開発されたのは1969年のことのようです。アーパネット(ARPANET)という世界で初めて運用されたパケット通信のコンピュータネットワークがその原型になったようです。パケット交換というのは、通信データをパケット(小包)と呼ばれる単位に分割して送信してつなぎ合わせる通信方法です。パケット交換による通信以前は、電話回線網のような回線交換によって通信が成り立っていたのです。
1982年にTCP/IT(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)が標準化されたことで、インターネットという概念が誕生し、そこから普及のスピードが上がったようです。1995年にWindouw95が登場した後で、初めて個人用のPCを買ったことを覚えています。その後はブロードバンド回線の普及、スマートフォンの普及も相まって、これら通信手段を使わない生活は考えられなくなりました。2G,3G,4G,5Gという言葉もありますが一定期間を経過ごとに、より高速で大容量の通信ができるように進化も続いています。
1990年前後から通信手段がどんどん変わっていくのは体感していました。外出が多い職種はポケベルを持つようになりました。その後は通信各社が携帯電話を販売するようになるとポケベルはなくなり、多くの人が携帯電話を持つようになりました。その少し前にはショルダーフォンという、肩にかけて持ち運ぶほど大きい携帯電話もありました。保険加入時の被保険者に対する診査訪問の際に、訪問診査をお願いした嘱託医の先生に貸していただいたことがありました。私が人生で初めて使った携帯電話です。
今回のブログで伝えようと思ったことは、急速な通信の進化や発展で人々の物事の考え方や意識が変化してしまったのではないかということです。私が少年期から学生時代、また社会人前半に考えていたことは大きく変化しました。その後は会社の業務に埋没して、本を読むことも少なくなりました。その当時をまだ、新しい知識を身に着けたいとの気持ちを持っていた青春時代を懐かしみながら、また、最近手にした「現代思想入門」(千葉雅也著 講談社現代新書)に触発されたこともあって、学生や社会人の初期に関心のあった思想などを振り返ってみようかと思いました。
3,知識人によって学生が影響を受けていた時代
戦後以降から1960年代くらいに学生たちに広がっていたのは、マルクス主義といわれる考え方だったと思います。私なりに理解をしているその考え方を表します。世界は物質により存在しているという唯物論の考え方を基本にする思想です。その社会では物質を支配者する上部構造と支配される下部構造に分かれていきます。支配する側と支配される側です。上部構造と下部構造の変更は、バトルによってのみ可能ですが、それが階級闘争です。物質の価値は労働によってもたらされます。上部構造に位置する資本家は、下部構造にある労働者の労働力によってもたらされる価値を搾取することで得られる利益で権力基盤を強化しています。その構造の変革は、権力闘争を経た革命によって得られると考えました。
次には哲学思想の話をしましょう。学生など若者に支持された哲学者にサルトルがいました。その思想の根幹は、人間は自由であり、自分の意志で生きていけるという考え方です。人間の実存(存在)そのものを主体とする考え方なので、実存主義と呼ばれました。人間は自由な存在であり、「自由の刑に処されている」とサルトルは表現しています。人間は自らを意味づけ行為を選び取り、自分自身で生きる意味を生み出すことを求めた哲学でした。主体的に自分を作っていくという考えは、知識人やエリート層には受け入れやすい考え方でした。
その西洋中心の思想によるサルトルを批判したのが、構造主義を打ち出したレヴィ=ストロースです。人間は自分の意志で生きているつもりでも、無意識のうちに社会や時代の考え方に縛られていると考えます。人間は地域や言語など構造に影響されて生きていますから、それらの構造によって意識も変化します。また、人類の親族関係はどんな構造(パターン)でできているかの研究から始め、閉じない社会にするために、近親婚がタブーになり、女性が違う集団に嫁ぐ交流の構造(パターン)を維持してきたとします。それが婚姻という構造です。人間社会はそのような構造に支配さていると解釈し、各国に残る神話などから構造を研究した哲学です。西洋文明が偉大で、未開文明が劣っているとはないと主張して。エリート中心で西洋中心の哲学を批判しました。
その後ポスト構造主義、あるいはポストモダンといわれる現代思想が登場します。社会人になっている時期でもあり、深く読書することもなくなりかけたころです。デリダ、ドゥルーズ、フーコーというフランスの哲学者が有名です。これらの思想の基本は、「二項対立の脱構築」と言っていいでしょうか。善と悪、内と外、必然と偶然など明確に分かれている概念が、実は必ずしも分かれているとは限らないという考え方です。脱構築というのは、二つの概念の対立の良し悪しをいったん留保しようとします。例えば順法と違法の間にあるグレーゾーンが存在する場合、どのように考えるかは人それぞれで、それこそが人生のリアリティーが現れるところです。人によって考え方は違っていることに照準を与えて、個々人のリアリティーを大切にしようとする考え方のように思います。
4,二項対立の脱構築という概念
ポスト構造主義やポストモダンという現在思想に触れました。デリダは概念の脱構築を提唱し、ドゥルーズは存在の脱構築、フーコーは社会の脱構築を提唱した哲学者です。今までの思想のように支配層である資本家、一方支配される労働者が対立する二項対立ではなく、二項対立では表現できない差異にも目を向けて社会を見つめ直そうという哲学です。二項対立するものであっても、それは単に途中経過であって完了したものではないと考えます。
今回は社会の視点で考えるためにフーコーの考え方を触れていきたいと思います。支配を受けている人たちはただ受け身なだけではなく、支配されることを積極的に受入れる構造もあることを指摘しています。権力は上から押し付けるだけではなく、下からそれを支える構造もあって、悪玉が誰かという発想自体が間違いだとします。
フーコーは現代社会の構造についても考えます。権力は「規律訓練型権力」に変化しているとします。人間を閉鎖空間に閉じ込め、時間で管理して、組織の歯車にすることで交換も簡単にできる集団を作ることができると考えます。訓練教育が支配のツールになるのです。その支配のポイントとして挙げているのが、「監視」、「制裁」、「試験」です。王政など絶対主義の時代は、恐怖を植え付けて支配をしていましたが、共和制以降は管理することで支配する構造になっているとしています。
個人が没個性化して、誰かに見られていると日々感じることで、他人の視線に管理される存在になるのです。その管理の典型的なものとして、一望監視施設「パノプティコン」という表現を使っています。監視する側はいつでも見えるが、監視される側は監視する側を見ることができない。そのため実際は見られていなくても、いつも見られているという精神状態になってしまいます。
日本社会も規制が徐々に厳しくなっているように思います。コンプライアンスという概念に縛られて、パワハラ、セクハラなど秩序を乱すものを排除するなど規制が強化されています。以前に比べてダメなものと正しいものの線引きがはっきりしています。現代思想の二項対立の脱構築という考え方は、物事を固定的に評価するのではなく変化するものとしてとらえて、多様性を認めようという考えが根底にあります。しかしながら、ネット社会、SNSが急速に発達した社会は、巨大なビッグテック企業が人々の消費行動や個人情報を入手でき、人々をコントロールしやすくなっています。その点ではネット社会が現代の管理者ともいえるかもしれません。
5,ネット・SNSに依存する諸問題
インターネットの進化や通信技術の進化を見ながら、それ以前に若者を中心に影響を与えてきた哲学の話をしてみました。しかし、時代は知識人やエリートが人々の考え方に影響を与える時代から、それぞれの人が興味あることを見つけ、共感できる考え方を選ぶように変化しています。
特に2024年は選挙の年といわれましたが、米国トランプ氏の再選、兵庫県斎藤知事の再選などある面で不思議な選挙現象がありました。インターネットやSNSなど通信技術を利用した選挙が、今までとは違った現象を生んでいるように見えます。
私の若いときにかかわった哲学は、新聞、雑誌、書物、テレビによる知識の吸収によってなされました。ところが今ではネットやSNSによる情報の収集に代わっています。オールドメディアからニューメディアに代わる中で、雑誌や新聞の休刊、廃刊が続き、本屋さんも減少が続いています。人々が利用する情報もジャンルは通信技術の進歩によって大きく変化しました。
電車に乗っていても、以前は新聞や雑誌や文庫本を読んでいる人がたくさんいました。現在はそんな人は数少なくなり、代わりにほとんどの人がスマホを触っています。多くの人が起きている時間帯をスマホの操作に使っており、現代人はスマホがないと生きていけないくらい重要な生活のツールになっています。
そのような人々の生活がメディアの変化で現在の様式になりました。そこには大きな問題が起ころうとしています。それはデマ、陰謀、悪意の拡散です。検証されてもいない事象を投稿することで、間違った内容が拡散されることも増えています。個人的な思い込みで投稿された内容は、情報の受け手による思い込みも加わり、事実とは異なった方向に進むこともあります。それが原因で自殺する悲劇も報道されています。
ネットやSNSを多用するメディア操作に長けた人たちは、自分に都合の良い物語を作り、人々を単純に洗脳する力があります。現代思想で述べた「二項対立の脱構築」ではない、善と悪の単純対立が描き出されています。深く考えることなく感覚的に発信された内容は、単純な「善と悪」が作り出され、自分が「善」のほうにいて、「悪」を批判することに安心を感じるのでしょうか。
オールドメディアが主流の時代は時間をかけて活字に向き合い、理性的な思考をしようと努力が必要な時代でした。しかし、ニューメディアは人々を依存症にさせて、脳内物質を分泌させて、より一層の依存性を生み出すように仕向けられています。依存傾向が強くなると、現実や事実よりも快楽をもたらす対象を取り込もうとするようになります。
以前ベストセラーになった「スマホ脳」(アンデシュ・ハンセン著・新潮新書)でもスマホに依存する現代人が陥る危険性について述べられています。スマホやSNSは子供の脳の発達を遅らせて、思考力や記憶力に悪影響を及ぼすと伝えています。SNSは人と繋がっているようで、逆にリアルな繋がりが阻害されて孤独になるとも言います。人間本来は運動によって生活する生物なので、スマホの利用は制限して、運動時時間を作り、睡眠時間を守ることで、集中力を高め心の不調を予防できると伝えています。
元来人類の脳は狩猟や採集生活に適応するようになっており、通常の睡眠時間を確保して、適度な運動と食事をすることで身体や脳の健全性が維持できるのです。人類の脳は現代のデジタル社会に適応するようにはなっていないとして、過度にスマホ依存することに警鐘を鳴らしています。現代の通信手段のおかけで便利な生活ができるようになりましたが、人間という生物にとって良いかどうかは今後検証されていくでしょう。
現代社会がデジタル化に進む中で、自由度が増しているように感じますが、監視する技術もますます進歩しています。米国も中国もロシアも一般の人たちは強い国を求めている傾向が強いと思います。今後ますます権力が強固になることで、秩序を維持する方向性が強くなり始めています。強いものにあこがれることで、人々は支配される安心感を得ているのでしょうか。人との差異を許容できることも生きやすい社会であるように思いますが、時代はそのような方向に向かっていない気がします。
以上